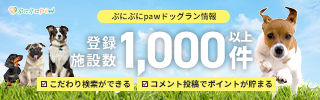「犬と一緒にもっと楽しく運動したい!」そんな飼い主さんに人気なのが、 ドッグスポーツ「アジリティ」 です。 アジリティとは、犬が飼い主の指示に従いながら、 ハードル・トンネル・スラローム などの障害物をクリアし、 スピードと正確性を競う本格的な競技。運動不足解消にもなり、愛犬とのコミュニケーションが深まる魅力的なスポーツです。 SNSや動画で見かけて、「うちの犬でもできるの?」と気になったことはありませんか? 実は、アジリティは特定の犬種だけができるものではなく、 初心者でも楽しめるドッグスポーツ です。 室内でも簡単に始められる方法があり、シニア犬や小型犬でも無理なく挑戦できます。 本記事では、アジリティの 基本ルール や 向いている犬種、そして 初心者が始めるための準備とトレーニング方法 を詳しく解説します。 「犬と一緒にできる運動が知りたい!」「アジリティを始めたいけど何からすればいい?」そんな方にぴったりの内容です。 愛犬と一緒に 新しいチャレンジ を始めてみませんか?
本記事の内容

1.アジリティとは?競技の基本を知ろう 2.アジリティに向いている犬の特徴 3.うちの犬はアジリティ向き?適性チェックリスト 4.アジリティを始める前にやるべき基本トレーニング 5.アジリティの練習を始める方法 6.おわりに
1.アジリティとは?競技の基本を知ろう

アジリティとは?
アジリティは、犬と飼い主が一緒に楽しめるドッグスポーツのひとつです。
コース内にはハードル、トンネル、スラローム(ジグザグのポール)などの障害物が設置されており、犬は飼い主の指示を頼りに、決められた順番でこれらをクリアしながら走ります。
競技では「スピード」と「正確性」が重視され、ゴールまでのタイムを競うだけでなく、ミスなく障害をクリアすることもポイントになります。
アジリティの魅力
- 初心者でも始めやすい:運動不足解消やしつけの一環としても人気。
- 犬と一緒にできるスポーツ:愛犬とのコミュニケーションが深まる。
- 幅広い犬種が挑戦可能:競技会(JKC、OPDESなど)に参加する本格派から、ドッグランや自宅で楽しむ人まで多様。
アジリティ競技の特徴
① スピードと正確さが重要
アジリティは「犬と飼い主が一緒に楽しめるスポーツ」であり、タイムを競うだけでなく、障害物を正確にクリアすることも評価基準になります。
- ジャンプ、スラローム、トンネルなどの技術が求められる。
- 運動能力だけでなく、犬のしつけや集中力も鍛えられる。
② 飼い主と犬の信頼関係が試される
犬は「ハンドラー(指示を出す飼い主)」の声やジェスチャーを頼りにコースを進みます。そのため、アイコンタクトやコマンドトレーニングが重要になります。
アジリティを通じて飼い主との絆が深まり、しつけにも役立つドッグスポーツです。
③ 初心者でも楽しめる
アジリティは競技会に参加するだけでなく、以下のような方法でも気軽に楽しめます。
- 初心者向けアジリティ教室:プロの指導で基礎から学べる。
- アジリティ設備付きドッグラン:自由に練習できる環境。
- 自宅での簡単な練習:ハードルやスラロームの代用品を使ったトレーニング。
アジリティができる場所
① 公式競技会(JKC、OPDESなど)
本格的に競技に挑戦したい人向け。JKC(ジャパンケネルクラブ)やOPDES(国際犬訓練競技会)が主催する大会では、犬種ごとのクラス分けもあり、初心者から上級者まで楽しめます。
② アジリティ設備のあるドッグラン
全国には「アジリティ専用フィールド」や「アジリティ設備付きドッグラン」があり、競技に挑戦する前の練習や体験に最適です。
初心者でも気軽に試せるため、まずはこうした施設を利用するのがおすすめです。
③ 自宅での練習
ハードルの代わりに低めのバーを使う、スラロームをペットボトルで代用するなど、「手作りアジリティコース」を自宅に作って練習することも可能です。
- 狭いスペースでも基本的なしつけや障害物トレーニングを取り入れられる。
- 初心者でも愛犬と楽しく練習できる環境を作れる。
2.アジリティに向いている犬の特徴

アジリティは 「犬と飼い主が一緒に楽しめるドッグスポーツ」 ですが、特に適性の高い犬にはいくつかの特徴があります。
運動量の多い犬種や、指示をよく聞く犬 は競技に向いており、しつけやトレーニングの一環としても効果的です。
アジリティ向きの犬種
運動能力が高い犬種:
ボーダー・コリー、シェットランド・シープドッグ(シェルティ)、ジャック・ラッセル・テリア などは、俊敏性があり、ジャンプやスピードを活かせるため、競技会でも活躍しやすい犬種です。
小型犬でも活躍できる犬種:
トイプードル、ミニチュアシュナウザー、柴犬 など、小型ながらも運動能力が高く、飼い主とのコミュニケーションを楽しめる犬種もアジリティに向いています。
作業意欲が高く、指示をよく聞く犬:
ウェルシュ・コーギー、オーストラリアン・シェパード などは、もともと牧羊犬としての役割を持ち、飼い主の指示に従うのが得意なため、アジリティ競技でも優れたパフォーマンスを発揮します。
アジリティに向いている性格
飼い主の指示に従うのが好き:
アジリティでは、犬が飼い主の声やジェスチャーに従いながらコースを走るため、コマンドトレーニングが得意な犬 は特に向いています。
好奇心が旺盛で新しいことにチャレンジするのが得意:
アジリティのコースは毎回異なるため、新しい障害物やコースに対して積極的に取り組む性格の犬 ほど楽しめます。
運動量が多く、遊ぶのが大好き:
日頃から 散歩だけでは物足りない、走るのが好きな犬 は、アジリティに向いている可能性が高いです。
3.うちの犬はアジリティ向き?適性チェックリスト

アジリティに挑戦したいと思っても、「うちの犬に向いているのかな?」と不安に感じる方も多いでしょう。実際には、犬種だけでなく、性格や運動能力、しつけの習熟度も適性に影響します。以下のチェックリストを参考に、愛犬がアジリティ向きかどうか確認してみましょう。
アジリティ適性チェックリスト
- ✅ ① 運動が好きで活発な性格か?
毎日の散歩でも元気いっぱいに走る、ボール遊びが大好きな犬はアジリティに向いています。 - ✅ ② 飼い主の指示を聞くのが得意か?
「待て」「おいで」などのコマンドにしっかり反応できる犬は、アジリティの練習がスムーズに進みます。 - ✅ ③ 物怖じせず、新しいことに挑戦しやすいか?
トンネルやスラロームなど、初めての障害物に対して好奇心を持って挑戦できる犬は、成長しやすい傾向があります。 - ✅ ④ 健康状態に問題がないか?
足腰に負担のかかる運動もあるため、関節に不安がある犬やシニア犬は無理をさせないことが大切です。
すべてに当てはまらなくても大丈夫!
アジリティは、トレーニング次第でどんな犬でも楽しめるスポーツです。「うちの犬は少し怖がりかも」「指示を聞くのが苦手」という場合でも、基礎トレーニングを積むことで克服できることが多いです。愛犬のペースに合わせて、少しずつ挑戦してみましょう!
4.アジリティを始める前にやるべき基本トレーニング

アジリティを始める前に、犬と飼い主のコミュニケーションを深める基礎トレーニングを行いましょう。アジリティは単なる運動ではなく、「指示を聞く力」や「集中力」も重要です。以下の基本トレーニングを取り入れることで、アジリティの練習がスムーズに進みます。
アジリティ前の基礎トレーニング
① 「待て」「おいで」などの基本コマンドをマスターする
アジリティでは、犬がコースを走る途中で「止まる」「進む」といった指示を正確に理解する必要があります。
- 「待て」ができると、スタート位置でしっかり待つ練習ができる
- 「おいで」を完璧にすると、飼い主の誘導がスムーズになる
- 「伏せ」「立って」などのコマンドも、コース内での細かい指示に役立つ
② 簡単な障害物(低いバーやトンネル)に慣れさせる
突然アジリティのコースに入れると、犬が驚いてしまうことも。まずは自宅やドッグランで、シンプルな障害物に慣れさせましょう。
- 床に棒を置いて、軽くジャンプさせる(低いハードル)
- ダンボールを並べて、トンネルのようにくぐらせる
- 椅子の脚などを使って、スラローム(ジグザグ歩き)を練習する
③ 飼い主とのアイコンタクトを強化する
アジリティでは、犬が「飼い主の動きや指示をよく見ること」が重要です。アイコンタクトを強化することで、犬がコース内でも落ち着いて指示を待てるようになります。
- おやつやおもちゃを使い、「目が合ったらご褒美」を繰り返す
- 声だけでなく、手の合図(ハンドシグナル)を教える
- 「アイコンタクト → コマンド → 動作」の流れを意識する
基本トレーニングが成功のカギ!
これらのトレーニングを身につけることで、アジリティ競技でもスムーズに指示を出せるようになり、犬の理解度が向上します。
いきなり本格的なコースに挑戦するのではなく、まずは「遊びながらトレーニング」することを意識しましょう!
5.アジリティの練習を始める方法

アジリティは、初心者でも「ドッグラン」「アジリティ教室」「自宅での簡単な練習」など、さまざまな方法で気軽に始められます。いきなり競技会を目指すのではなく、遊びながら練習を積み重ねることがポイントです。まずは愛犬が楽しめる方法で挑戦してみましょう!
アジリティを始める方法
① 自宅でできる簡単な練習
特別な設備がなくても、自宅にあるものを使ってアジリティの基礎を身につけることができます。
- 椅子を並べてスラロームの練習
→ 「アジリティのスラローム(ジグザグ走行)」を再現し、犬に飼い主の指示に従って動く練習をさせる。 - 布団や箱を使ってトンネルの練習
→ 初めは短めのトンネルから慣れさせ、少しずつ長くすることで恐怖心を克服できる。 - 低いハードルを使ったジャンプ練習
→ 本格的なハードルがなくても、床に棒を置いたり、クッションを使ったりすることでジャンプの基礎練習が可能。
💡 ポイント:自宅での練習は「遊びながら楽しく」が重要!
最初から完璧にできなくてもOK。成功したらおやつや声掛けで褒めて、ポジティブな経験を積み重ねることが大切です。
② 初心者向けのアジリティ教室を探す
アジリティの基礎をしっかり学びたい場合は、ドッグスクールや専門のアジリティ教室でのトレーニングがおすすめです。
- 近くのドッグスクールで体験レッスンを受ける
→ 「アジリティ初心者向けレッスン」を実施している施設が多く、基本動作やコースの回り方を学べる。 - アジリティができるドッグランを利用する
→ 「アジリティ設備付きのドッグラン」では、自由に練習しながら楽しめる。まずは簡単なコースから試してみると良い。
💡 ポイント:愛犬に合った環境を選ぶ
「教室で基礎を学んでからドッグランで練習」など、愛犬の性格や成長段階に合わせて進めると、ストレスなくアジリティを楽しめるようになります。
6.おわりに

アジリティは、どんな犬でも挑戦できるドッグスポーツ です。 「運動神経が良くないと無理かも」「うちの犬は怖がりだから…」と不安に思っている方も、心配はいりません。それぞれの犬に合った方法で楽しめるのがアジリティの魅力です。 初めて挑戦する場合は、いきなり競技会を目指すのではなく、「遊び感覚で楽しむ」ことが大切 です。まずは、基本のしつけ(「待て」「おいで」など)や軽い運動 から始めて、少しずつ障害物に慣れさせていきましょう。 アジリティは、犬の運動不足解消やストレス発散 にも役立つだけでなく、飼い主との信頼関係を深める素晴らしい機会 になります。一緒に目標を持ち、成功を共有することで、愛犬との絆がより強くなる のも、このスポーツの魅力です。 「もっと本格的に挑戦してみたい!」という方は、JKC(ジャパンケネルクラブ)やOPDES(国際犬訓練競技会) などが主催する競技会にエントリーすることもできます。競技のルールやエントリー方法については、JKC公式サイト や OPDES公式サイト をチェックしてみてください。 「うちの犬もアジリティできるかな?」と気になった方は、まずは 自宅での簡単なトレーニング から始めてみましょう。また、アジリティ教室や設備のあるドッグランで体験してみる のもおすすめです。 遊びながら練習を続けることで、きっと愛犬も楽しんでくれるはずです。
JKC公式サイト: https://www.jkc.or.jp/
OPDES公式サイト: https://www.opdes.jp/
~関連記事~
● 愛犬と楽しむスポーツ!フライボールとは?
● 犬と楽しむ「おやつキャッチ」の教え方
● イヌとの散歩がもたらす健康効果