SFTS(重症熱性血小板減少症候群)はマダニによって媒介されるウイルス性疾患です。 犬にも人にも感染リスクがあり、ときに命に関わる重篤な症状を引き起こします。 近年、ペットの感染例が増えており注意が必要です。 本記事では、獣医師監修のもと、犬のSFTS感染による症状や予防策をわかりやすく解説します。
この記事の監修
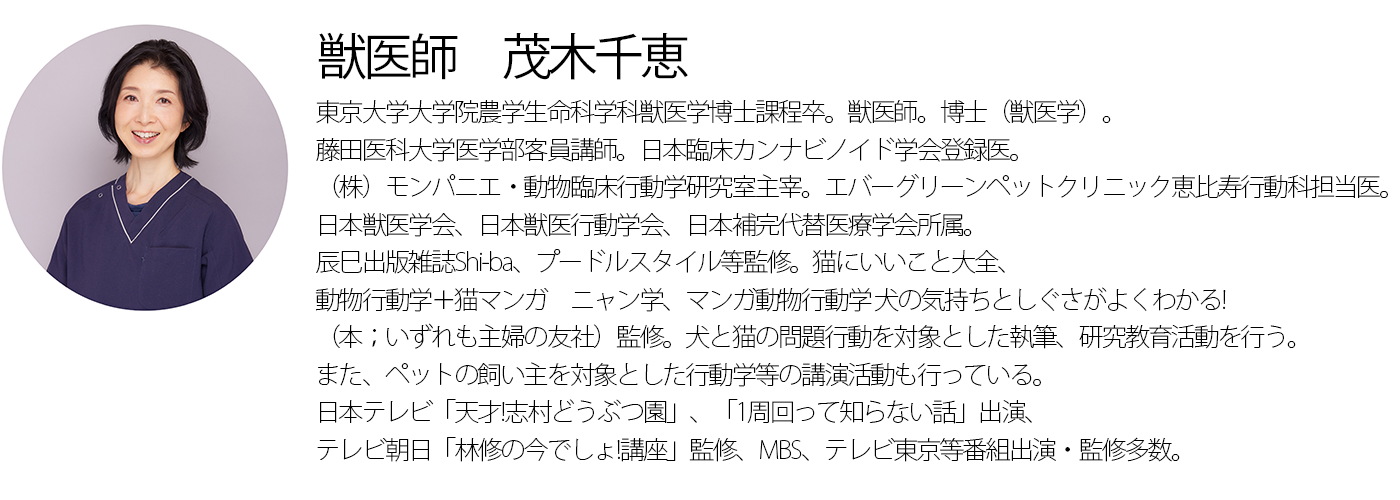
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)とは?

SFTSとはどのような病気か、その原因や特徴をまず押さえておきましょう。
SFTSはどんな病気?原因ウイルスと症状の特徴
「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」は、マダニを媒介して感染するウイルス性の病気です。
日本国内でも近年西日本を中心に患者報告があり、現在は感染症法では四類感染症に位置付けられています。感染者は国に報告され、人数が把握されています。
国内では主にニホンジカ、イノシシ、アナグマ、アライグマなどの野生動物がFSTSウイルスを保有しており、マダニはこのような動物に寄生吸血することで、体内にウイルスを取り込んでしまいます。
マダニは草むらや森林などに生息し、付近に立ち寄った犬や猫にも寄生することがあります。
SFTSに感染すると、高熱、元気消失(沈うつ)、食欲不振、嘔吐、下痢といった症状が現れます。
また、血液検査で白血球や血小板(止血に必要な成分)の著しい減少が認められる点も特徴です。発症した場合に致死率が高い深刻な疾患であり、早期発見と治療が重要になります。
人獣共通感染症としてのSFTS
SFTSは人獣共通感染症(ズーノーシス)であり、犬・猫・人のすべてが感染し得ます。
2025年3月末時点では国内の猫では1023頭、犬では64頭の発生が確認されています。
通常はウイルスを保有するマダニに咬まれることで感染しますが、動物から人への感染事例も報告されています。
実際、2025年にはSFTSに感染した猫を治療した獣医師がSFTSを発症し死亡するケースが確認されました(後述)。
猫のSFTSは特に致死率が高く、約60%が命を落とすとの報告があります。
犬でも重症化することがあり、重症例では致死率が40%に達するとのデータがあります。
人の場合も致命率は20〜30%に上ります。
このようにSFTSは動物から人へもうつるため、ペットを含めた総合的な対策が求められます。
参考:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について|厚生労働省
関連記事
愛犬をダニから守る!犬にダニが付かない方法4選愛犬にダニがいるのを見つけた!緊急時の対処法も解説
【2025年最新】SFTS感染が全国で拡大中|猫・獣医師・人への感染事例も

国内のSFTS患者発生数は増加傾向にあり、過去に1000名以上の感染が確認されています。 2023年には年間134例と過去最多を記録しました。 2025年に入ってからは、ペットの感染が関東で初めて確認されたことや、獣医師や人の死亡例が報じられるなど、SFTS拡大に関する深刻なニュースが相次いでいます。 ここでは最新の事例について整理します。
茨城県|関東初のペット感染を確認
2025年5月、茨城県で屋内飼育されていた猫がSFTSに感染し死亡しました。
一時的に屋外へ脱走した際にマダニに咬まれたと見られており、ペットのSFTS感染が関東地方で確認された初めてのケースとなりました。
さらに同県では6月、登山によく連れて行かれていた3歳の飼い犬が40℃を超える発熱や食欲不振などの症状を示し、血液検査で白血球・血小板の低下が確認されました。
その後の詳細な検査により、この犬もSFTS陽性と判明しています。
幸い犬は治療により回復しましたが、茨城県内では猫に続き2例目のペットSFTS感染例となり、関東でもマダニ媒介感染症への警戒が必要だと報道されました。
三重県|SFTS感染猫を診療した獣医師が死亡
2025年春、三重県でSFTSに感染した猫の診療にあたっていた獣医師が体調不良を訴えました。
発熱、倦怠感、呼吸困難などの症状が出て入院しましたが、数日後に残念ながら死亡しています。
身体にマダニに咬まれた痕はなく、SFTS陽性だった猫の血液や唾液との接触によって感染した可能性が高いとされています。
動物の診療が原因で獣医師が死亡した例は国内で初めてとみられ、この事態を受けて日本獣医師会は全国の獣医師に向け注意喚起を行いました。
ペットの飼い主にとっても他人事ではなく、感染動物の体液を介した人への感染リスクに改めて警鐘が鳴らされた事件です。
犬のSFTSの症状と受診の目安

SFTSは重篤化が早いため、早期発見・早期治療が非常に重要です。 愛犬の異変にいち早く気付き、適切に対処するために、犬のSFTSの症状と受診の目安を確認しておきましょう。
犬の主な症状と進行・鑑別ポイント
犬がSFTSを発症した場合、急にぐったりして元気がなくなり、食欲不振や40℃前後の発熱といった症状が現れます。
嘔吐や下痢などの消化器症状が約半数にみられ、脱水に陥るケースもあります。
血液検査ではCRPマーカー(犬の場合)の上昇、白血球や血小板の著しい減少を伴う炎症反応が認められます。
SFTSが進行すると、意識混濁(ふらつきや反応低下)などの神経症状が現れることがあります。
猫では黄疸がよく見られます。
発症した場合、SFTSは短期間で急速に悪化し、ほとんどが発症から7日以内に死亡します。
そのため、症状が軽いうちに適切な対処をしないと命に関わる危険性があります。
発熱初期に治療を開始できれば回復の可能性が高い感染症です。
ただし、犬の場合は発症しない、あるいは発症しても1日で熱が下がるなどの症例が多く、SFTS感染に気づかないまま経過することもあります。
似た症状との違いを見極めるポイント
これらの症状は他の犬の病気(胃腸炎や熱中症など)と似ているため、区別が難しい場合があります。
そのため、最近草むらを散歩した、あるいはマダニに咬まれた可能性がある場合は、SFTSの可能性を考慮する必要があります。
実際、SFTSに感染した犬でマダニの寄生が確認されたのは12%未満であり、マダニ駆除剤を使用していても発症したケースも報告されています。
したがって、日頃からのマダニ予防と散歩後の被毛チェックに加え、一般的なウイルス感染への対策も重要です。
こんなときは迷わず動物病院へ
愛犬に上記の症状が見られ、1日経っても改善しない、あるいは急速に悪化する場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。
特に、真夏ではないのに40℃前後の高熱が出てぐったりしている、激しい嘔吐や下痢が起きているといった状態は深刻なサインです。
マダニに咬まれた可能性がある場合は、必ず獣医師に伝え、SFTSなどの感染症の可能性について相談してください。
2025年現在、SFTSに有効なワクチンや確立された治療薬はありません。
そのため、早期に輸液や対症療法などの適切な処置を受けることが、回復の可能性を高めます。
「おかしいな」と感じた時点でためらわず専門家の診察を受けることが、愛犬の命を守ることにつながります。
愛犬のSFTS感染を防ぐには?飼い主さんができるマダニ対策

SFTSから愛犬を守るためには、マダニに刺されないようにすること、そしてマダニを屋内に持ち込まないようにすることが、最も重要な予防対策です。 飼い主さんが日々実践できるマダニ対策のポイントをご紹介します。
マダニ対策の基本は予防薬と環境管理
最も確実な予防策は、動物病院で処方されるマダニ予防薬を定期的に投与することです。
犬用のスポットオン(滴下薬)、経口薬、首輪型の駆虫剤など、ペットの生活環境に合った製剤を獣医師と相談して選びましょう。
マダニが繁殖しにくい環境を整えることも重要です。
庭や散歩コースの草むらにはなるべく近づかせず、自宅周辺の草刈りや除草をこまめに行いましょう。
落ち葉や藪など、マダニが潜みやすい場所を減らすことで、愛犬への寄生リスクを下げることができます。
同居している犬や猫からの感染経路も報告されています。
もし1頭が発症した場合、飼育環境にすでにSFTSウイルスが入り込んでいるとみなし、消毒や感染拡大の阻止に努めることが必要です。
散歩後のチェックで早期発見
愛犬が屋外での散歩やアウトドア活動をした後は、マダニが身体に付いていないか毎回確認する習慣をつけましょう。
ブラッシングをしながら、耳の周り、首輪の下、脇の下、指の間などを特に注意深く観察してください。
マダニはゴマ粒から米粒くらいの大きさの黒っぽい節足動物で、被毛に隠れて吸血している間は気づきにくいことがあります。
散歩後、犬の体表をマダニが歩いている段階で発見できれば、吸血される前に取り除くことが可能です。
これだけでも感染リスクを大幅に減らせるため、早期発見と早期除去が非常に重要です。
なお、SFTSウイルスは一般的な消毒で死滅させることができます。
エタノールや次亜塩素酸などの薬液、加熱、UV照射などによる消毒で清浄化しましょう。
マダニを見つけたらどうする?
愛犬からマダニを見つけたら、ピンセットや専用器具を使い、頭部を挟んでゆっくりまっすぐ引き抜くことが重要です。
指で潰したり、無理にねじったり、ハーブオイルやアルコール、火で炙るなどの方法は避けてください。
除去後は傷口を消毒し、マダニは密閉して廃棄します。
除去が困難な場合や、一部が皮膚に残った場合は、動物病院を受診しましょう。
人への予防も忘れずに
SFTSを含むマダニ媒介疾患は人にも深刻な被害を及ぼします。
草むらや山道では、長袖、長ズボン、帽子に加え、ディート配合の虫除けスプレーを使用することで、マダニ予防効果を高めることができます。
ただし、ディートは高濃度(80%以上)の製品を犬が直接吸入したり経口摂取したりすると、神経症状(ふらつき、けいれんなど)を引き起こす可能性が報告されています。
使用時は
(1) 屋外または換気の良い場所で自分の体から20 cm以上離して噴霧し、犬を近づけない、
(2) スプレー後は液が乾くまで犬と接触しない、
(3) 犬と触れ合う前に手を洗い、帰宅後は衣服も早めに洗濯する
――この3点を徹底してください。
イカリジン(ピカリジン)を有効成分とする製品
犬と暮らす家庭では、イカリジン(ピカリジン)を有効成分とする製品も選択肢となります。
イカリジンは、蚊やマダニなどの害虫を寄せ付けない効果があり、犬の散歩時やアウトドアでの使用に適しています。
海外でも、イカリジンは犬を含むペットにも使用できる虫除け成分として知られており、ディートよりも毒性が低いと評価されています。
ただし、犬に使用する際には、必ず犬用の製品を選ぶことが重要です。
人間用の虫除けを犬に使うと、誤飲や皮膚への刺激などのリスクがあるため、注意が必要です。
その他の予防策
虫除けスプレーの使用だけでなく、野外活動やペットとの外出後には、自分の衣服や皮膚にマダニが付着していないか確認し、可能であれば帰宅後すぐにシャワーを浴びることも効果的です。
また、万が一ペットがSFTSに感染した場合、飼い主さんへの二次感染予防が重要です。
SFTSウイルスは、感染した動物の血液、唾液、吐瀉物、排泄物などの体液を介して人に感染する可能性があります。
看病時には以下の感染防止策を徹底してください。
- 素手でペットに触れない
- 嘔吐物や排泄物の処理時は、アイガード(フェイスガード)、手袋、マスクを着用する
- 使用したペットシーツはビニール袋に密閉して廃棄する
- 看病する人を限定する
- 徹底した手指の洗浄を行う
犬の場合、症状が治まった後も尿や糞便中にウイルスを3週間以上排出し続ける可能性があるため、治癒後もしばらくは排泄物の扱いに注意が必要です。
飼い主さん自身の身を守ることは、結果的に愛犬の命を守ることにも繋がります。
看病中に発熱や倦怠感などを感じた場合は、ためらわずに医師の診察を受け、SFTS感染の可能性を伝え、治療を開始してください。
まとめ

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は致死率が高く、人にもペットにも脅威となり得る新興感染症です。 近年は国内での広がりが懸念されており、西日本に限らず関東を含む各地で注意が必要です。 しかし、過度におびえる必要はありません。 飼い主さんが適切なマダニ予防策を講じることで、愛犬のSFTS感染リスクを大きく低減できます。 日頃から予防薬の定期投与や散歩後のボディチェックを欠かさず行い、万一異変があれば早めに動物病院を受診してください。 SFTSについて正しい知識を持ち、備えを万全にすることで、これからも愛犬とのお出かけを安心して楽しむことができるでしょう。












