愛犬がいつもと違った音を出して咳をしていると心配になりますよね。 犬も人間と同じように喉や気管が刺激されれば咳をしますが、たまに出る程度の咳なら様子見でも、何日も続く咳は油断できません。 本記事では咳の特徴、原因、対処法、予防法について、獣医師の知見に基づき解説します。 早期の受診目安や、ご家庭でできるケアについてもご紹介します。
この記事の監修
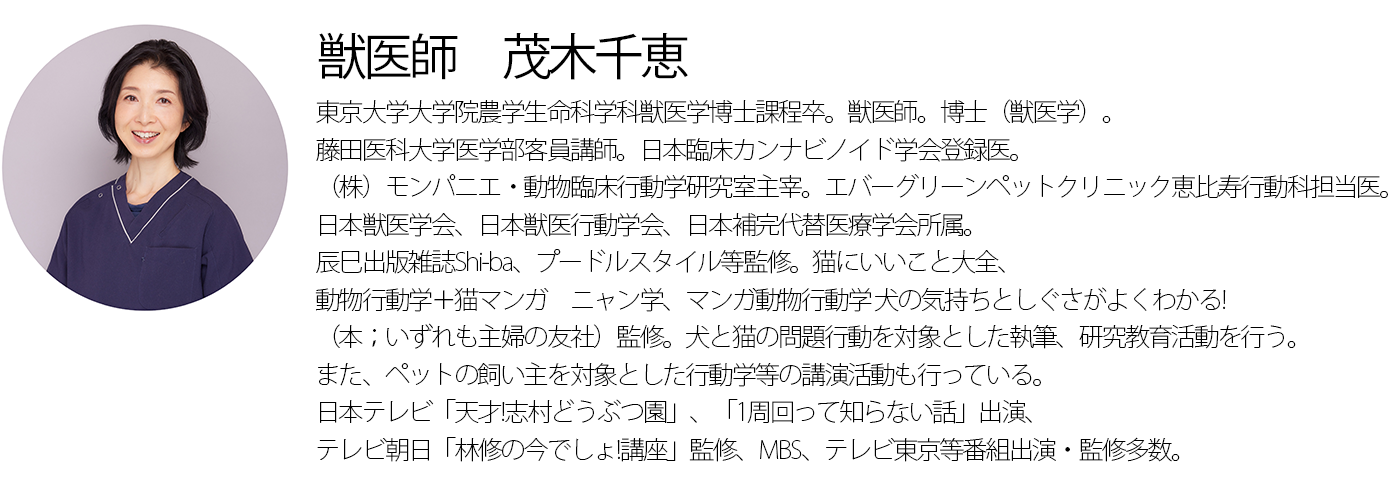
犬も咳をする?咳の特徴と見分け方
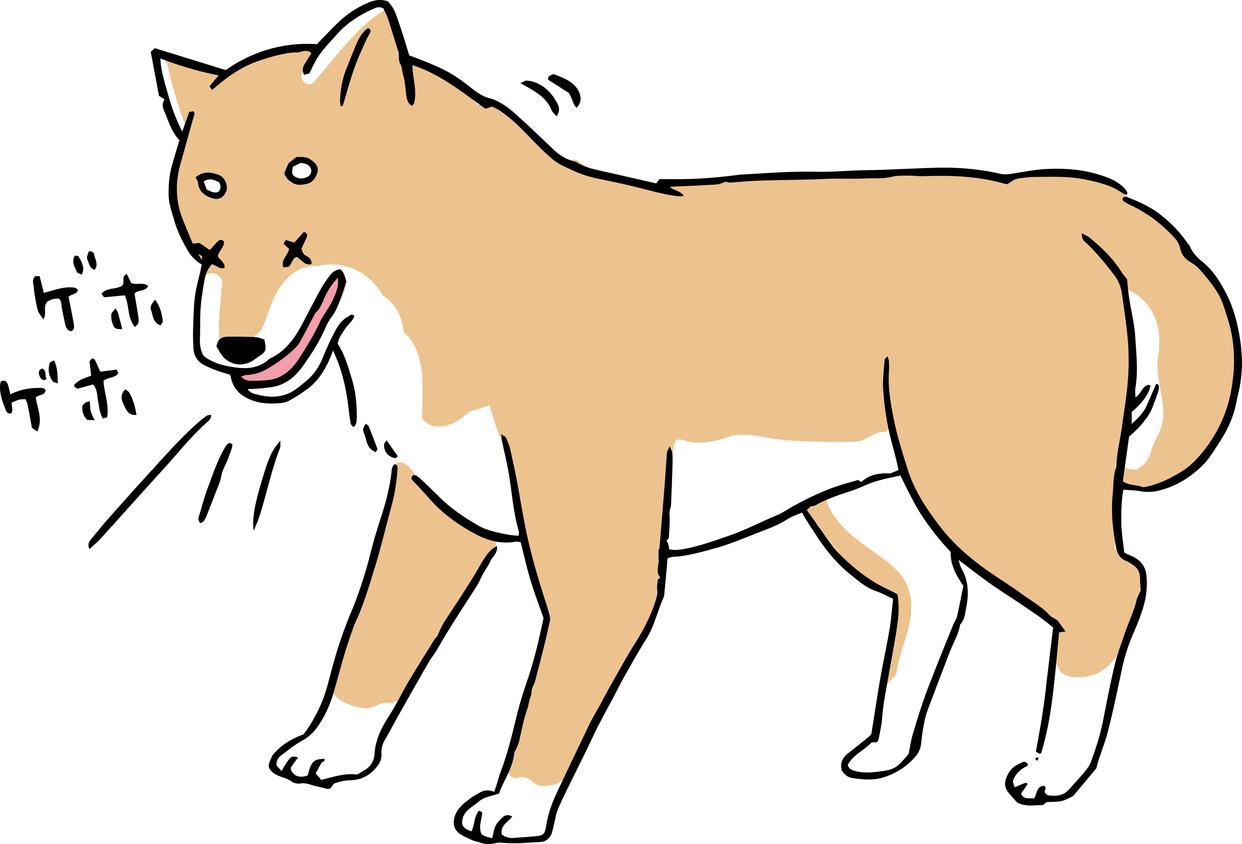
犬の咳は、人間とは少し違った特徴があります。 まずは、咳と似た症状(くしゃみや吐き気)との違いや、咳が出やすいタイミングなど、基本的な見分け方を解説していきます。
犬の咳はどんな音?くしゃみ・吐き気との違い
犬の咳は「カッカッ」「ゴホゴホ」といった乾いた音や、「ガーガー」というアヒルの鳴き声のような音が特徴で、粘液や泡状の唾液を伴うことがありますが、食べたものが出てくる嘔吐とは異なります。
くしゃみは「クション!」と鼻から息を出す動作で、鼻腔の異物を排出するためのものです。
一方、「逆くしゃみ」は鼻から急激に息を吸い込み「ブーブー」「ガーガー」と音を立てる一時的な反応で、一見すると咳に似ていますが、息苦しさはほとんどなく、すぐに収まる場合は無害です。
これらの症状の判断が難しい場合は、動画を撮って獣医師に相談してみましょう。
関連記事:犬の逆くしゃみとは?発生理由や病気との見極め方を紹介
どんな時に咳が出やすい?
犬の咳は、運動直後や興奮、遊びなどで呼吸が荒くなる状況と、首輪を強く引っ張った際などに起こりやすくなります。
夜間から明け方(睡眠後)に悪化することもあり、これは就寝中に気道に分泌物が溜まるためと考えられています。
また飼育環境も影響します。
空気が乾燥する時期や季節の変わり目は、空気中のチリ・ホコリで咳が出やすくなります。
冬の暖房による乾燥や夏の高温多湿、ホコリやタバコの煙も気道を刺激し、咳を悪化させることがあります。
慢性気管支炎の犬では、天候や環境ストレスで症状が悪化することも。
このように咳が出る状況を観察することは、原因究明の手がかりになります。
犬の咳に考えられる主な原因とは?

咳の原因は軽い環境要因から重大な病気まで様々です。 ここでは可能性のある主な原因を、一般的に症状が軽いものから重篤なものへと順に解説します。 愛犬の様子と照らし合わせ、当てはまる症状があれば早めに動物病院で診てもらいましょう。
環境要因(乾燥・ハウスダストなど)
犬の咳は、冬場の空気の乾燥、ホコリ、煙、ハウスダスト、花粉、香水、掃除用スプレーなどの環境要因で起こります。
特に、ホコリの多い部屋や喫煙環境では気管支炎を引き起こしやすいです。
軽度の咳は原因がなくなれば治まりますが、環境が悪いままだと慢性化する可能性があります。
咳が気になる場合は、まず室内の湿度を40から60%に保ち、頻繁に掃除をしたり、空気清浄機などを使ったりして原因物質を取り除くことが重要です。
改善しない場合は、他の病気の可能性も考慮してください。
気管虚脱
犬の「ガーガー」と聞こえる咳は、気管虚脱の可能性があります。
これは、気管が狭くなる進行性の病気で、チワワやポメラニアンなどの小型犬に多く見られます。
興奮時や運動時、首に負荷がかかった時などに咳が顕著になり、安静にしていても咳が持続し、ゼーゼーと笛を吹くような喘鳴(ぜんめい)が聞こえるケースや、呼吸困難や失神を起こしてしまう重症ケースもあります。
根本治療はないものの、体重管理や薬で症状を抑えられます。
重症の場合は気管にステント(筒状の器具)を入れる外科手術で気管の閉塞を軽減できる場合もあります。
このような咳が続く小型犬は、早めに動物病院を受診しましょう。
異物の誤飲・誤嚥
犬が激しい咳をする原因の一つに、おもちゃや食べ物の誤嚥があります。
特に子犬は異物を喉に引っ掛けやすく、「カッ、カッ」という高い音の咳をして苦しがってパニック症状を見せます。
これは緊急事態であり、気道が完全に塞がると命に関わるため、ただちに異物を除去する必要があります。
意識がある場合は噛まれる危険があるため注意が必要ですが、意識がない場合は迷わず口腔内を確認し見える異物を取り除いてください。
異物誤嚥の疑いがあるときは速やかに動物病院へ向かいましょう。
応急処置で異物を吐き出せても、気管や喉粘膜が傷ついて炎症や腫れを起こす危険があります。
誤飲しやすい性格の犬や子犬を飼っている方は、普段から誤食事故に注意し、おもちゃ選びや環境整備(床に物を落とさない等)を徹底してください。
気管支炎や肺炎
気管支炎は、ウイルスや細菌感染(ケンネルコフなど)によるものや、アレルギー、刺激物の吸入が原因で発症します。
数日で治る急性気管支炎とは異なり、慢性気管支炎は2か月以上咳が続き、原因が特定できないのが特徴です。
特に小型犬に多く見られ、完治が難しいとされています。
加齢、受動喫煙、大気汚染など長年の気道刺激が関与し、乾いた空咳が長期化し、悪化すると吐くようにえづくことがあります。
肺炎は、細菌やウイルスが肺に達して炎症を起こす重篤な状態です。
湿った咳に加え、元気消失、発熱、食欲不振などの全身症状を伴います。
子犬や高齢犬は免疫力低下のため進行しやすく、呼吸困難になる危険があります。
横になれない程の苦しさ、ひどい咳と鼻水・膿性鼻汁、胸から湿った音が聞こえるなどの重症化の兆候が見られる場合は、速やかな治療が必要です。
心臓病(僧帽弁閉鎖不全症など)
高齢の小型犬の咳が続く場合、心臓病、特に僧帽弁閉鎖不全症の可能性を考慮すべきです。
これは心臓弁の機能不全によるもので、乾いた咳(「コン、コン」)を引き起こし、横臥時や夜間に悪化しやすいです。
進行すると肺水腫や呼吸困難に至る危険があります。
また、運動不耐性(運動したがらない、疲れやすい、ふらつく)を伴うこともあり、進行すると頻呼吸、腹水、体重減少などの全身症状が現れます。
慢性心不全は完治しませんが、投薬治療で症状を管理できます。
中高齢犬で咳が続く場合は、心臓検査(聴診、レントゲン、エコーなど)を強くお勧めします。
ケンネルコフ(犬風邪、うつる可能性あり)
ケンネルコフは、犬の「風邪」で感染力が非常に強いです。
特徴的な症状は激しい乾いた咳(「カハッカハッ」)で、喉に何かが引っかかっているような音や、えづきを伴うこともあります。
感染犬との直接接触だけでなく、おもちゃや食器を介しても感染するため、不特定多数の犬が集まる場所では注意が必要です。人には感染しません。
ケンネルコフが疑われる場合は、愛犬を安静にし、他のペットから隔離してください。
軽症なら7〜10日で自然治癒しますが、咳が続く間は感染力が強いため、他の犬との接触を避ける必要があります。
症状が悪化したり長引いたりする場合は、早めに動物病院を受診しましょう。
動物病院を受診するべき症状とは?

咳をしているとき、どのタイミングで受診すべきか悩む飼い主さんも多いでしょう。 軽い咳なら自宅ケアで様子見でも構いませんが、放置できない兆候もあります。 ここでは受診の目安として、「様子見で良いケース」と「早めに受診すべき症状」の例を示します。
様子見でよいケース
以下のような場合は、もう少し自宅で様子を観察してもよいでしょう。
●1〜2回、単発で咳をしただけで、その後けろりとしている。
●咳以外は元気・食欲が普段通りである。
●興奮や運動時に一時的に咳が出たが、安静にしたら治まった。
咳以外の状態(呼吸数・元気さ・食欲飲水など)が正常なら、48〜72時間程度は経過を見守って構いません。
その間に咳が悪化しなければ、ひとまず深刻な異常ではない可能性が高いです。
早めに受診すべき症状
次のような症状が見られたら早急に受診してください。
●咳が数日以上続いている、または徐々に回数・激しさが増している。
●咳がひどく夜も眠れない、食事や水飲みの邪魔になるほどである。
●発熱(平熱は犬で38〜39℃程度)や鼻水・くしゃみなど他の症状を伴う。
●呼吸が浅く速く、ゼーゼー苦しそうにしている(呼吸困難)。
●舌や歯茎の色が紫色〜灰色に変化した(チアノーゼ)。
上記のような場合、何らかの病気が進行しているサインと考えるべきです。
特に呼吸困難やチアノーゼは緊急状態で、一刻も早く診察を受ける必要があります。
咳をしている犬への家庭での対処法

愛犬が咳をしているとき、飼い主が家庭でできるケアをいくつか紹介します。 ただし応急的な対処であり、治療の代わりにはなりません。 症状が続く場合は必ず獣医師の診断を仰いでください。
安静にさせる
興奮や運動は咳を誘発するため、散歩や激しい遊びは中止し、静かな室内で休ませてください。
家族も大きな物音を立てたり興奮させたりしないように協力しましょう。
ケージやサークルに入れて落ち着かせるのも有効です。
犬が咳をしているときに背中をなでることは、犬を落ち着かせる目的で行う分には問題ありませんが、咳の治療や症状の改善には直接的な効果はありません。
重い症状が見られる場合は、必ず獣医師に相談してください。
空気を清潔&加湿する
乾燥した空気は咳を悪化させる一因のため、加湿器を使って適度な湿度(50〜60%程度)を保ちましょう。
湿度を上げることで気道の粘膜が潤い、咳の緩和に役立ちます。
ネブライザーという吸入器を使って獣医師が処方する薬剤を吸わせる方法が効果的です。
室内のホコリはこまめに掃除機をかけて除去し、犬が咳をしている間は喫煙や芳香剤の使用は控えてください。
空気清浄機も活用してクリーンな環境を保つことで、咳の緩和に繋がります。
抱っこや首輪の扱いに注意
咳をしている犬には、体の扱い方にも配慮が必要です。
まず、抱っこする際は胸や腹部を圧迫しないよう十分注意しましょう。
咳込んでいる最中に強く抱きしめると呼吸が妨げられ、状態が悪化する恐れがあります。
犬が自分で楽な姿勢をとれるようサポートするのが良いでしょう。
特に気を付けたいのが首輪の扱いです。
咳が出ているときや気管に持病がある犬には、首輪ではなくハーネス(胴輪)を使用するのがおすすめです。
また、興奮して引っ張ると咳込む犬の場合は、しつけリードなどで引っ張りグセを制御する工夫も良いでしょう。
治療が必要な病気だった場合の対処と費用目安
診察の結果、もし病気が判明した場合は治療が必要となります。
ここでは、代表的な治療内容の例と、それに伴う費用の目安、およびペット保険の活用法についてご紹介します。
治療内容の一例
犬の咳の治療法は原因により様々ですが、代表的なものを紹介します。
- 内科治療(投薬): 咳を和らげる鎮咳薬、気管支の腫れを抑える消炎剤(ステロイド)、心臓病による咳には強心剤や利尿剤など心不全の薬が用いられます。気管支拡張薬が有効なケースもあります。
- 酸素吸入・ネブライザー: 呼吸状態が悪い場合、酸素室での酸素吸入や、薬剤を霧状にして吸わせるネブライザー療法を行います。
- 検査: 病因の究明には、胸部レントゲン検査、血液検査、麻酔下での気管支洗浄液の採取や気管支鏡検査などが必要です。
- 外科治療: 重度の気管虚脱には気管ステント留置術、僧帽弁膜症には外科手術が選択肢となることがあります。
費用の目安とペット保険の活用
咳の治療にかかる費用は、原因となる病気の種類や治療内容によって大きく異なります。
初診料と基本的な検査(身体検査・レントゲン・血液検査など)でおおよそ5,000〜15,000円前後が一つの目安です。
例えば、軽い気管支炎でレントゲンと飲み薬だけなら1万円程度で済むこともありますが、重度の肺炎で入院治療や酸素室管理が必要になれば数万円〜十万円以上になるケースもあります。
経済的な負担に備えるために、ペット保険の利用も検討しましょう。
ペット保険は、契約内容によって治療費の50%〜70%程度を補償してくれるのが一般的です。
ただし、病気が見つかってからの加入では既往症が補償対象外となるケースが多いため、愛犬が健康なうちに早めに検討することをおすすめします。
予防のためにできること

最後に、日頃からできる咳の予防策についてまとめます。 咳の原因となる病気を未然に防ぎ、愛犬が快適に過ごせるよう以下のポイントに気をつけましょう。
定期的な健康診断を受ける
早期発見・早期対処のためには、定期的な健康診断が不可欠です。
年1〜2回、獣医師によるチェックをおすすめします。
特に7歳以上のシニア犬は年2回程度の頻度で受診し、心音や呼吸音、血液検査などで咳の原因となりうる心臓や肺の異常を早期に発見しましょう。
定期健診によって基礎的な健康データが蓄積されるため、異変があった際に獣医師も「以前と比べてここがおかしい」と気づきやすくなります。
定期的な健康診断は、愛犬の健康を総合的に評価し、問題が深刻化する前に発見するのに役立つとされています。
ワクチン接種(ケンネルコフなど)
犬の混合ワクチンは、ジステンパー、アデノウイルス2型、パラインフルエンザウイルスなど、ケンネルコフの原因となる病原体に対するものが含まれます。
接種により発症リスクが下がり、重症化を防ぐ効果が期待できます。
ワクチンスケジュールは子犬期から始まり、成犬でも年1回の追加接種が推奨されます。
ドッグランやペットホテルではワクチン証明書の提示が求められることもあり、未接種だと利用できない施設もあります。
愛犬と周囲の犬のためにも、必要なワクチンは必ず受けさせましょう。
生活環境の見直し
日頃の生活環境を整えることも咳の予防につながります。
まず、掃除・換気をこまめに行い、犬が長時間過ごす部屋は清潔で快適な空間にしましょう。空気清浄機や加湿器の活用も有効です。
特に冬場は乾燥対策を、夏場は高温多湿に注意し、エアコンで室温・湿度を調整するなど、季節に応じた工夫をしてください。
次に適度な運動と体重管理も重要です。肥満傾向にある犬は呼吸器や心臓に余計な負担がかかり、咳の原因疾患(気管虚脱や心不全など)を悪化させるリスクがあります。
ただし急激なダイエットや運動のしすぎも禁物ですので、犬種や体調に合った無理のない運動習慣を心がけてください。
さらに、散歩時にはハーネスの使用を検討しましょう。
喉に直接圧をかけない構造のハーネスは、気管へ負担を減らすことができます。
最後に、ストレスの少ない生活も咳の予防に一役買います。
ストレスで免疫力が低下すると感染症にかかりやすくなり、また気管虚脱などは興奮で症状が悪化します。
愛犬の性格に合った環境づくり(留守番時間の配慮や過度な叱責をしない等)を心掛け、心身ともに健康でいられるようサポートしてあげてください。
まとめ
犬の咳は一瞬で終わってしまうと見過ごされがちですが、病気が隠れていた場合、放置すると重篤な状態になることもあります。
「ただの咳」と油断せず、 少しでも様子が変だと感じたら早めに動物病院で相談してみてください。
早期発見・早期治療が、愛犬の健康と快適な生活を守る第一歩です。












