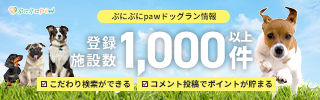この記事でわかること ・犬にも「生理(ヒート)」があり、初回ヒートは平均6〜12か月齢で迎えます。 ・ヒートはおおむね2〜4週間続き、出血量・おりものの色・行動が段階的に変化します。 ・出血が本当にヒートなのか、子宮蓄膿症や膀胱炎など命に関わる疾患なのかを早く見極めることが大切です。 ・ヒート中はドッグランやトリミングサロン利用を避け、同居の未去勢オスとは別室管理を徹底しましょう。 ・本記事では正常なヒートの目安と、すぐ動物病院へ行くべきサインを紹介。 ヒート未経験の飼い主さんが事前に準備すべき物や出血対策も紹介します。
この記事の監修
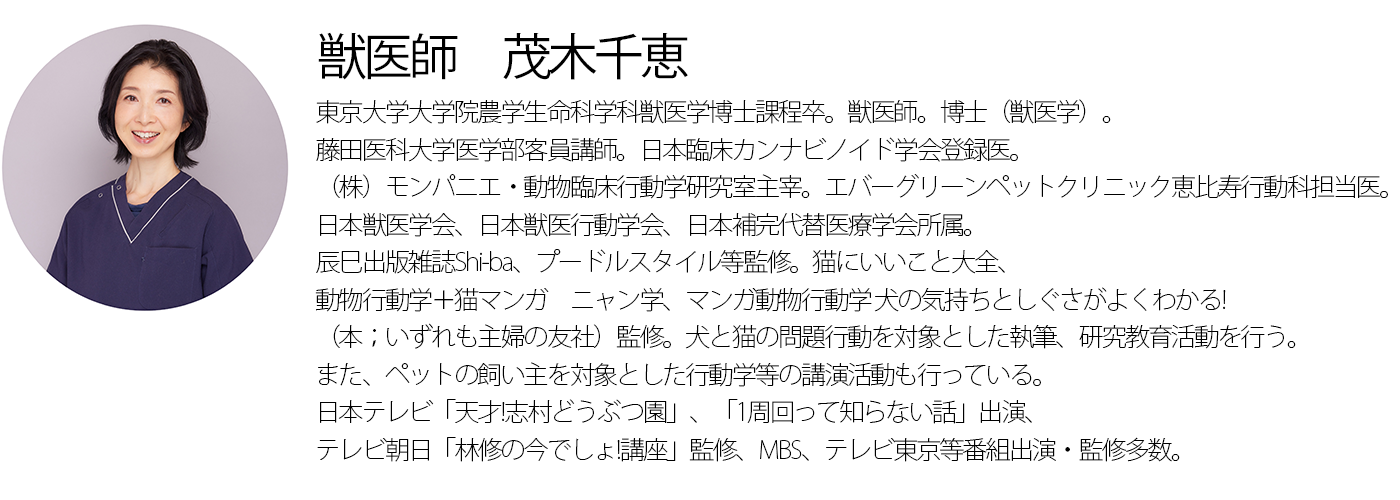
1. 犬の生理(ヒート)と発情期の基礎知識
ヒートは4つの時期が周期的に繰り返します。人とは周期も出血する時期も異なります。
| 時期 | 期間の目安 | 主な所見 | 行動の変化 |
| 発情前期 | 7–10 日 | 陰部が腫れ、分泌物が増える | オスが来ても交尾拒絶 |
| 発情期 | 5–10 日 | 出血が薄桃色に変化・減量 | 交尾受容、排尿マーキング増加 |
| 発情休止期 | 約60 日 | 分泌が止まり腫脹軽減 | 妊娠・偽妊娠・母性行動 |
| 無発情期 | 90–150 日 | 外陰部は通常の大きさ | 行動と体調が安定 |
ヒート終了から1~2ヶ月後に、乳腺の張り・巣作り・母性行動が現れることがあります。
これは卵巣から分泌されるホルモンの影響をうけた偽妊娠と呼ばれる自然な変化です。
多くは発情期から約2か月後に治まりますが、乳腺が大きく腫れたり、飼い主さんへの攻撃性が強くなったりする場合は治療が必要です。
避妊手術をするとヒートは来なくなり、子宮・卵巣疾患のリスクをほぼゼロにできます。
避妊手術は初回ヒート前後の6〜7か月齢までに行うと乳腺腫瘍の発生率を大幅に下げられますが、近年は品種・体格によって肥満のリスクが高まる避妊術実施時期があるとの研究報告も出ています。
高齢犬になってからの避妊手術のリスク
高齢犬の手術には注意が必要です。
成犬期以降は麻酔リスクが高まり、術後の回復も若齢期より遅くなるため、すでに子宮蓄膿症や乳腺腫瘍を併発しているケースでは手術が大掛かりになり、身体的負担も費用も大きくなりがちです。
こうした理由から、健康な若齢期に計画的に避妊手術を行うことが、愛犬にとっても飼い主さんにとっても最も安全で負担の少ない選択肢といえます。
2. 犬の生理はいつから始まる?

一般的には6から14か月齢で始まります。 ただし個体差が大きいため、多少前後することが有ります。 目安の時期を過ぎても初回出血がない場合は先天性卵巣欠損・内分泌疾患などを疑い受診してください。
3. 犬の生理は何歳まである?
犬には閉経がなく、高齢になっても卵巣が機能すればヒートが来ます。
ただし加齢で間隔が延び、出血量が減るのが一般的です。
12歳を超えて突然ヒートが来なくなった場合は卵巣腫瘍・全身性疾患を疑います。
逆にシニア期に短い周期で出血を繰り返す場合はホルモン異常による子宮等の疾患を疑い、超音波(エコー)検査が推奨されます。
4. 犬の生理は何日間?
ヒート全体で平均2〜3週間。うち出血が目視できるのは1~2週(平均9日)間です。
生理期間が7日未満の場合は、無排卵発情やホルモン分泌の異常が疑われます。
生理が4週間以上続く場合は、卵巣嚢腫や子宮疾患などのトラブルが隠れている可能性があります。
まずは動物病院で相談してください。
特に長すぎる場合は、腹部エコー検査と血液検査でホルモン(エストロゲン・プロゲステロンなど)の異常値が無いかどうか調べてもらったり、さらなる精密検査をしたりして、検査結果に基づいた治療方針について獣医師と相談しましょう
5. 生理周期の頻度
犬の生理は一般に年2回、つまりおよそ6か月間隔で訪れるのが標準ですが、体格や犬種によって大きく幅があります。
たとえば小型犬では間隔が短くなることがある一方、大型犬では間隔が長くなる傾向です。
またバセンジーのように年1回となる例もあります。
もし周期が極端に乱れる場合は注意が必要です。
具体的には、前回の出血から3か月も経たないうちに再びヒートが来るようなら、子宮蓄膿症などの疾患やホルモン異常が原因となっていることがあります。
また、反対に12か月以上まったくヒートが来ない場合は、卵巣機能の低下や重度の全身性疾患が関与している可能性があります。
いずれの場合も早めに動物病院を受診し、エコー検査や血液検査などで基礎疾患の有無を確認することが大切です。
6. 生理中の犬に見られる主な症状とケア

ヒート中の犬は次のような普段と異なる行動を見せることがあります。
・元気がない・眠そうにしている
→散歩距離を半分以下に。静かな場所にベッドを置く。
・食欲低下
→温めたウェットフードや香りの強いトッピングを少量ずつ使う。
・陰部を頻繁に舐める
→清潔なペットシーツを敷き、陰部周囲の被毛を短くカットしておく。
・尿マーキング・落ち着きが無い
→サークル等で行動範囲を狭める。一緒に遊んだり知育トイなどで気を逸らしたりする。
・甘え・夜鳴き
→就寝場所を飼い主の近くへ移動する。スキンシップを多めにとる。
これらはホルモンの大きな変化によって自然に起こってくるものですので、時間の経過とともに軽くなっていくことが多いですが、次のような症状がみられる場合はすぐに動物病院へ相談しましょう。
必ず受診したい症状
- 39.5 ℃以上の発熱・じっとして動かない、触ろうとすると噛みつくなどの強い痛み
- 嘔吐(空えずきも含む)・下痢が24 時間以上続く
- 臭いを伴った粘性の高い分泌物が陰部から出ている
- 排尿時出血・頻尿
- 大量出血
これらは子宮蓄膿症・膣炎・膀胱炎などの徴候です。
7. 注意したい生理中の異常サインと疑われる病気
次のようなサインは病気が疑われます。同時に起きている不調も併せて獣医師に相談しましょう。
・血混じりの分泌物が出て悪臭がする
→ 疑われる病気:子宮蓄膿症
→ 併発しやすい症状:発熱、大量の水を飲む、腹部膨満
・少量の出血(おりもの)が長期間続く
→ 疑われる病気:膣炎
→ 併発しやすい症状:陰部を気にする・舐める
・排尿の終わり際に血が混じる
→ 疑われる病気:膀胱炎・尿路結石、膣炎
→ 併発しやすい症状:頻尿、排尿時の痛み、血液塊の排出
・出血と同時にお腹が風船のように膨れる
→ 疑われる病気:卵巣腫瘍、腹水
→ 併発しやすい症状:食欲不振、呼吸が速い
8. 生理中の過ごし方

・散歩コース
他犬が多い公園は避け、早朝・深夜の人通り少ない時間帯を選ぶ。
・同居している未去勢のオスとの隔離
犬の場合、出血終了後6日目から10日目(発情期入り後)は、妊娠の可能性が高まります。
オス犬を遠ざけるべき期間は、一般的に発情期から2週間程度が推奨されます。
ただし、出血が始まってから発情期入りするまでの期間は犬によって異なるため、妊娠を望まない場合は、いつから再会できるかを獣医師に相談することが重要です。
・外出先の利用制限
ドッグラン・ホテル・サロンの多くはヒート犬の入場を禁止しています。予約時に必ず申告しましょう。
・出血対策
市販の犬用パンツ・オムツを使用し、2~4 時間ごとに交換するのがおすすめです。
オムツかぶれ防止に陰部と周囲をぬるま湯で洗浄して乾かしてから再装着します。
・シャンプー・ワクチン
全身入浴は避け、陰部周囲のみ清拭しましょう。
ワクチン接種や避妊手術などの全身麻酔処置はヒート後体調が落ち着いてからになります。
かかりつけの獣医師に相談しましょう。
9. 犬の生理に関するよくある質問
9‑1. 陰部がとても腫れていて心配です
ヒート前期は通常の2〜3倍に膨れて柔らかくなります。
触って極度に痛がる・紫色に変色してきた場合は炎症やけがを疑い受診を。
9‑2. 初めての生理が早い/遅い
3か月齢未満の場合は性ホルモン異常、18か月齢を超える場合は卵巣発育不全などの可能性があります。
いずれも一度検診を。
9‑3. 出血量が多い気がします
人用ナプキン換算で1日に1枚以上濡れる場合は多いでしょう。
貧血や子宮粘膜病変の恐れがあるため動物病院での検査を推奨します。
9‑4. 避妊手術後なのに出血が…
避妊手術から数ヶ月以上経っている場合、卵巣遺残症候群(卵巣組織の取り残し)や生殖器腫瘍からの出血が考えられます。
膣スメア(膣内分泌物)の顕微鏡検査で発情出血かどうかを確認し、エコー+血液検査(ホルモン測定)で確定診断します。
9‑5. 自分の血を舐めてしまいます
少量なら健康被害は少ないですが、過度な舐めは陰部の皮膚炎の原因に。
他のおもちゃやスキンシップで気持ちを逸らしましょう。
皮膚炎になっていたり、夜中も眠れないくらい気にしたりしているときはオムツ装着に加えてエリザベスカラーの併用も検討します。
9‑6. オムツは必要?
床や家具への付着量、犬の舐める頻度や皮膚炎が起きているかなどを含めて判断します。
少量なら吸水シーツで代用できます。おりものが多くて気になる時期はサイズに合った犬用パンツを準備すると良いでしょう。
9‑7. オムツを噛む/食べる
マナーベルト型やサスペンダー付きおむつカバー製品を使う、薄手の伸縮ウェアやカバーオール型の犬服で覆うなどの対策もできます。
9‑8. オムツ以外の出血対策は?
犬用サニタリーパンツなどの中に人用の吸収ライナーを取り付けるなども可能ですが、誤食には十分に注意しましょう。
犬用ベッドなどの上に防水シーツを敷いたり、古タオルを掛けたりすることで後処理を簡便にすることができます。
|
[ユニ・チャーム] マナーウェア 女の子用 EわんEにゃん |

SSS、SS、S、M、Lサイズまでご用意! |
|
【M-PETS】女の子用おむつ ペットグッズ専門店Petifam |

おしゃれな柄のおむつ。XS、S、M、L、XLサイズまでご用意! |
10. まとめ

動物病院へ行くべきサイン
- 39.5 ℃以上の発熱や極度のぐったり感
- 悪臭や膿を含む分泌物、または水っぽい大量出血
- 出血が「7日未満で終わる」あるいは「4週間以上続く」
- 24時間以上続く嘔吐・下痢・過剰な水分摂取・多尿
- 下腹部が急に膨らむ、あるいは触ると強い痛みを示す
上記のいずれかに当てはまる場合は、自己判断せず早めに受診してください。
飼い主さんが日常でできること
1.健康手帳をつける
初回ヒートの前から、出血の色・量・日数や行動の変化をアプリやカレンダーで記録しましょう。
小さな違和感でも「前回と比べて変だな」と気づきやすくなり、異常の早期発見につながります。
2.高齢期でも油断しない
シニア犬でもヒートは続くのが普通です。
出血量が減ったからといって安心して健康診断を後回しにすると、子宮蓄膿症など重篤な疾患の発見が遅れる恐れがあります。
疑問があれば獣医師と相談を。
3.環境と体調の管理
ヒート中は未去勢オスとの接触を避けましょう。
オムツやマナーベルトを使う際は2〜4 時間ごとに交換し、皮膚を清潔に保ちます。
食欲や散歩の意欲が落ちた日は無理をさせず休息を優先します。
ワクチンや長距離移動はヒート後しばらく経ってからが安心です。
4.周期が乱れたらすぐ相談
ヒートの間隔が3か月未満で再発する、または12か月以上来ないなどの周期の変化はホルモン異常や子宮・卵巣疾患のサインかもしれません。
放置せず、動物病院でエコー検査やホルモン検査を受けましょう。
ヒートは愛犬が見せてくれる大切な健康状態を知るサインです。
周期間隔や出血の状態を「見て・書いて・比べる」だけで、多くのトラブルを早期に防ぐことができます。
もし気になる症状があっても、早期に獣医師に相談すれば大事に至らないで済むケースは少なくありません。
飼い主さんの心がけで愛犬の安心で快適な毎日を守ってあげましょう。