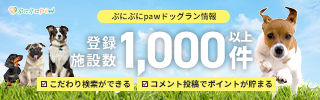「最近、やたらとうちの犬が水を飲んでいる気がする」 「すぐに水のボウルが空になり、何度も足しているけれど、こんなに飲んで平気なの?」 と不安を抱く飼い主さんは少なくありません。 実際、犬がたくさん水を飲むのは、暑さや運動量など一時的な理由による場合もあれば、病気やストレスが原因で“病的な多飲”を起こしている可能性もあるのです。 本記事では、どの程度の飲水量から「多飲」と判断できるかをはじめ、多飲を引き起こす主な病気やストレス要因などを詳しく解説します。 さらに、一見問題なさそうに見えても、念のため病院へ行ったほうが良いケースについても紹介します。 愛犬の健康を守るため、飲水量の変化をいち早くキャッチし、必要に応じて適切なケアや受診につなげましょう。
この記事の監修
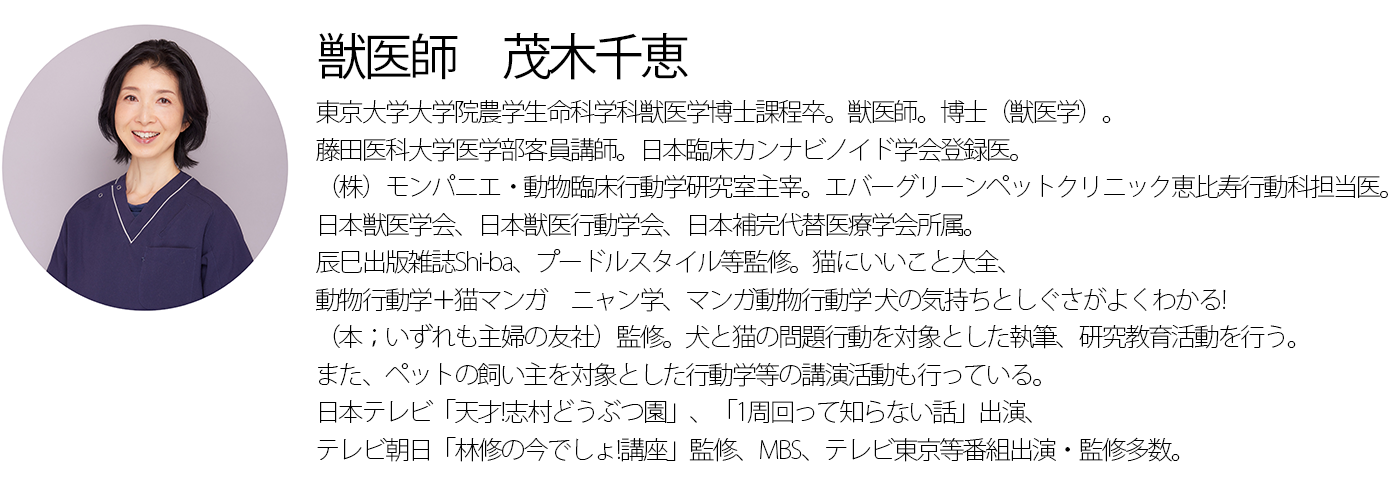
「水の飲み過ぎ(多飲)」と判断する基準
1-1. 犬の正常な飲水量と測り方
犬の飲水量は体格・年齢・気温・運動量などさまざまな要因で変動しますが、一般的には体重1kgあたり1日50~60mL前後が目安といわれています。
たとえば体重5kgの小型犬なら、1日に250~300mL程度がひとつの参考値です。
愛犬の飲水量を正確に把握するには、一日に数回行う水の入れ替えのタイミングごとに、ボウルに入れた水の量を計測し、次の入れ替え前に残った量との差を記録する方法がおすすめです。
常に新鮮な水を与えながら1日の総飲水量を把握できるので、異常があれば早期に気づきやすくなります。
1-2. どのくらいの量だと「多飲」といえるのか
もし飲水量が体重1kgあたり1日100mL以上に達するようであれば、“多飲”の疑いがあると考えられます。
とくに、以前より急激に水を飲む量が増えた場合は、何らかのトラブルが起きているかもしれません。
以下のような症状が併発していれば、迷わず動物病院を受診しましょう。
- 排尿回数が極端に増えた(多尿)
- 食欲低下や体重変化(増減)が顕著
- 嘔吐や下痢などの消化器症状がある
- 元気や活力がなく、遊びや散歩に興味を示さない
1-3. 飲水量以外に着目すべきポイント
多飲を見極める際には、「一度に飲む量が異常に多い」「短時間に何度も飲みたがる」といった行動面にも注目してみてください。
水の飲み方が急に荒くなったり、氷を舐めるのがやめられなくなったりするなど、いつもとは違うパターンが見られる場合は要注意です。
こうした変化は、単なる「喉の渇き」ではなく、ストレスや体調不良が隠れているサインかもしれません。
2. 注意したい「犬が水をよく飲む」原因とその見分け方

犬が水をたくさん飲む原因は実にさまざまですが、中でも病気やストレスが理由となっている場合は、放置すれば命に関わるケースもあります。 ここでは、特に注意すべき主な病気を中心に、その見分け方を紹介します。
2-1. 糖尿病
血液中の糖(血糖値)が高い状態が続くと、体は余分な糖を尿と一緒に排出しようとします。
その結果、大量の尿が作られるため、体内の組織の水分が奪われ、犬は強い喉の渇きを覚えて多飲になるのです。
糖尿病は肥満傾向の中高齢犬に多く、多飲多尿のほか体重減少や食欲の変化、白内障の進行などが見られることがあります。
早期診断と血糖コントロールが重要なので、気になる症状があれば早めに血液検査を受けましょう。
2-2. 慢性腎不全
腎臓の機能が低下すると、老廃物をうまく排出できなくなり、その埋め合わせとして大量に水を飲むようになります。
特にシニア犬に多く見られ、食欲不振・嘔吐・口臭の悪化・被毛のパサつきなどが併発する場合もあるのが特徴です。
一度低下した腎臓機能は回復しにくいとされるため、定期的な血液検査や尿検査を通じて早期発見に努めることが大切です。
2-3. 尿崩症
「尿崩症(にょうほうしょう)」は、尿の生成を減らす働きのある「抗利尿ホルモン」の分泌や機能に異常が起き、体内の水分を保持できなくなる病気です。
非常に大量の排尿と、それに伴う多飲が特徴で、放置すると脱水や体内のミネラルバランスの乱れが進行する危険があります。
原因は脳の下垂体と呼ばれる神経の障害や腎臓の機能異常などさまざまで、血液検査やホルモン検査で診断されることが多いです。
2-4. クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
副腎皮質ホルモンが過剰に分泌されることにより、多飲多尿・脱毛・食欲亢進・腹部の膨れなどさまざまな症状を引き起こす病気です。
主に中高齢の小型犬で多く見られますが、大型犬でも注意が必要です。
日常的に症状が続くので、単に「歳のせいかも」と見過ごさず、早期に検査を受けると治療効果が期待できます。
2-5. 子宮蓄膿症
メス犬特有の病気で、子宮内に膿が溜まるため多飲多尿を引き起こします。
陰部からの膿の排出、食欲不振、元気消失、発熱などの重症状が出やすく、進行すると命に関わるケースも少なくありません。
避妊手術をしていないメス犬が急に水をたくさん飲み始めたら要注意です。
3. 水をたくさん飲んでいても問題のないケース

必ずしも「犬が水をよく飲む=(イコール)病気」というわけではなく、一時的な気温・運動量・食事の変化などで多飲が起きることもあります。 飼い主さんとしてはすぐに元に戻ると一安心ですが、様子を自宅で見ているだけでそのうち治るのか、病気なのかの判別は自己判断が難しいため、不安な場合は迷わずに獣医師へ相談しましょう。
3-1. 季節や環境の影響
犬は人間のように体全体に汗腺がほとんど無いため、高温環境では口からの呼気で体温を下げようとします。
その結果、夏の暑さや冬の暖房による乾燥など気温・湿度の変化があると、一時的に水をたくさん飲むのは自然な反応です。
軽い脱水を補うため体が水分を欲している場合も多いため、適度に新鮮な水を与え、熱中症対策や室温管理をしっかり行ってください。
3-2. 活動量の増加
運動や遊びの時間が長くなれば、その分身体は水分を失います。
散歩やドッグラン、トレーニングなどで普段より長く動いた日は、飲水量が増えても不自然ではありません。
一度に大量に飲みすぎないよう、小まめに水分補給させるのがポイントです。
3-3. 食事の変化
ウェットフードからドライフードに切り替えたり、塩分の多い食べ物を与えたりすると、飲水量が増えることがあります。
再度食事を調整してみて、飲水量が元に戻るようであれば問題のない可能性が高いでしょう。
ただし、犬にとって過剰な塩分や偏った栄養は長期的に体調を崩す原因にもなるため、食事内容の見直しは定期的に行うよう心がけてください。
3-4. ストレス
引っ越しや家族の増減、留守番の時間が増えるなど、環境が大きく変わったタイミングで多飲が始まる場合、ストレスが影響している可能性があります。
ストレスによる一時的な多飲であれば、周囲の環境や飼い主さんの接し方を調整することで、徐々に落ち着いてくるケースが多いと考えられます。
たとえば、クレートやケージの上にブランケットをかけるなどして視界を狭めると、外の物音や人の動きを気にしすぎずに済むため、犬は「ここなら安心できる」と感じやすくなります。
また、食事や散歩、就寝などの日々のスケジュールをできるだけ一定の時間に揃えると、犬は先を見通せるようになり、余計な不安に陥りにくくなるでしょう。

さらに、日頃の散歩やドッグランなどでしっかりと運動させ、家の中では嗅覚遊びやパズルフィーダーなどで頭を使う機会を増やすと、心身ともに適度に疲労が生まれ、ストレスによる行動を起こしにくくなります。
犬が落ち着いている状態のときに優しく声をかけたり、ごほうびを与えたりすると、飼い主さんといることがより安心できるものだと学習しやすくなります。
ただし、犬が不安定な行動を取った直後にむやみに甘やかしてしまうと、その行動が強化される恐れがあるため注意が必要です。
また、室内の音環境や匂いにも配慮してあげると、犬のリラックスを促しやすくなります。
たとえば、静かな音楽やホワイトノイズを流せば、急な物音に過剰反応しにくくなるかもしれませんし、犬用のフェロモン製剤を試すことで落ち着きを取り戻すきっかけになる場合もあります。
ただし、犬が苦手と感じる匂いもあるため、獣医師と相談しながら慎重に導入すると安心です。
これらの方法を試しても、依然として多飲が改善しない、あるいは別の問題行動が増えてきたという場合は、単なるストレスだけではなく病気の可能性も排除できません。
違和感を覚えたら、迷わず動物病院へ足を運び、行動面に詳しい獣医師や専門トレーナーと連携しながら原因を探ることが重要になります。
3-5. 薬の副作用
ステロイド薬など、治療目的で投与している薬の副作用として多飲多尿が出ることがあります。
薬を勝手にやめるのは非常に危険ですが、気になるところがあれば、獣医師と相談しながら、薬の種類・投薬量の調整をしましょう。
4. まとめ

犬が水をたくさん飲む理由には、大きく分けて次の2パターン、「病気やストレスによる病的な多飲」と「一時的な環境や体調変化による多飲」があります。 どちらも飼い主さんが自己判断で「大丈夫」と思い込んでしまうと、重篤な病気を見落としてしまう危険性が否定できません。日頃から以下のポイントをチェックし、少しでも異変を感じたら動物病院で診てもらうようにしましょう。
- 体重1kgあたり1日100mL以上の水を飲む場合は多飲を疑う
- 飲水量が急激に増えた/減ったときは要注意
- 多飲に加えて多尿・嘔吐下痢・食欲不振・元気消失など他の症状があるときは早急に受診
- 季節や運動量、食事、薬の副作用など、一過性の理由で増えることもあるが、長く続くなら病気を疑うべき
愛犬の行動や様子を注意深く観察し、いつもと違うサインがあればためらわず専門家に相談することが、病気の早期発見・早期治療につながります。
犬の「水の飲み過ぎ」は、決して見過ごしてはいけない重要な健康チェックポイントのひとつ。小さな変化に気づいてあげることで、愛犬がいつまでも健やかに暮らせるよう、日頃からこまめな観察とケアを心がけてください。