犬に噛まれてしまうと、 「まず何をすればいいの?」 「病院に行かないとダメ?」 といった疑問や不安が一気に押し寄せてきます。 実際、犬の咬傷(こうしょう)は一見たいしたことのない傷に見えても、感染症のリスクがあり、放置すると症状が悪化する可能性も否定できません。 本記事では、犬に噛まれた際の具体的な応急処置や、病院を受診すべき基準、そして保健所への届け出など「今すぐやるべきこと」と「後から必要になるかもしれない手続き」について詳しく解説します。 「できれば病院に行きたくないけれど健康を損ないたくない」という方や、家族や知人が噛まれたときにとるべき対応がわからない方にも役立つ内容となっています。 この記事を最後まで読めば、犬に噛まれたときにまず何をすべきか、そしてどう行動すればよいかの判断材料を得られるでしょう。
この記事の監修
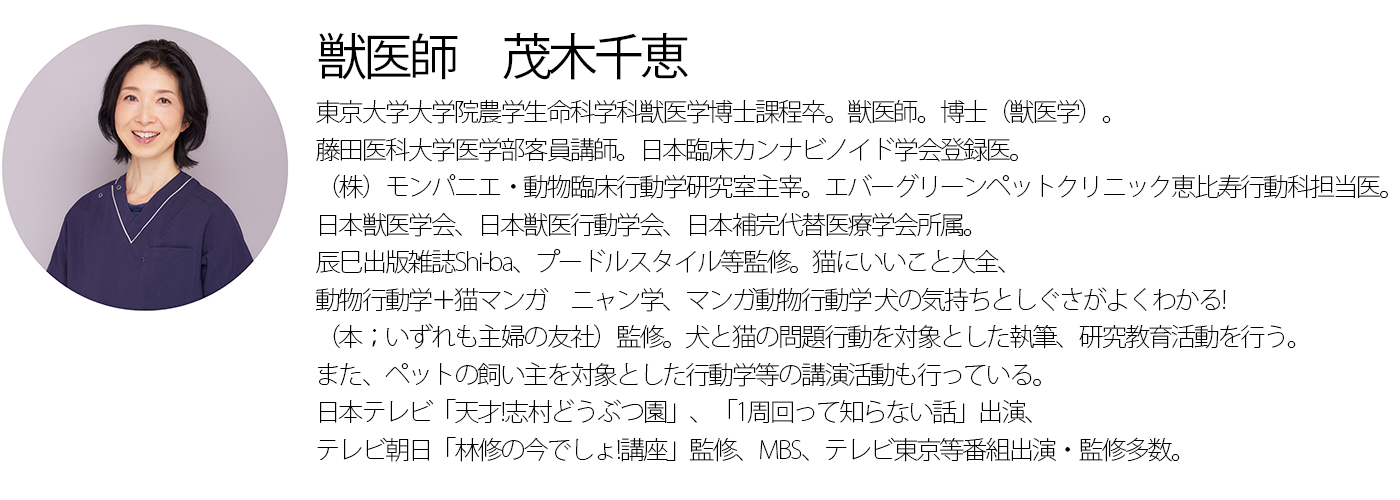
1.犬に噛まれた!まず「応急処置」をする

1-1.患部を流水で5分以上洗浄
犬に噛まれたら、まず最初に取り組むべきことは傷口の洗浄です。
犬の口内には数多くの細菌が生息しているため、傷口をそのまま放置すると感染症を引き起こすおそれがあります。
洗浄時には、流水を五分以上かけ流すようにして患部を十分にすすぎ、手元に薬用石けんやハンドソープがあれば活用すると効果的です。
ただし、傷口を強くこすりすぎると、かえって傷を広げてしまう場合があるため注意が必要です。
きちんと洗い流すことで細菌や汚れを物理的に取り除き、感染リスクを軽減しやすくなります。
特に、深い傷の場合はより丁寧に洗浄を行い、後々のトラブルを防ぐようにしましょう。
1-2.止血と保護
洗浄が終わったら、出血がある場合には清潔なガーゼやタオルで圧迫止血します。
激しい出血が見られない場合でも、患部にそっと押し当てるだけで血が止まりやすくなります。
ただし、ガーゼやタオルを必要以上に強く押し当てすぎないように注意してください。
血が止まったら、乾いたガーゼなどで傷口を軽く覆い、保護します。
なお、密閉度の高い絆創膏や防水パッドなどで完全に塞いでしまう方法は避けるほうがよいです。
空気の通りが悪くなると、細菌が繁殖しやすい環境を作ってしまう可能性があるため、注意が必要です。
1-3.応急処置で「やってはいけないこと」
応急処置の段階では、傷口を無理に押し広げたり、消毒液を大量に流し込んだりすることは避けてください。
このような行為は痛みを強めたり、組織を傷つけたりする可能性があります。
また、アルコール消毒のみで済ませるのも好ましくありません。
応急処置としては、まず流水による物理的な洗浄が最優先となります。
なお、これらの応急処置はあくまでも「暫定的な対策」です。
傷が深い、腫れが強いなどの不安要素がある場合は、できるだけ早めに病院を受診することを検討しましょう。
2.小さな傷でも病院には行くべき?受診を迷ったときの判断基準

犬に噛まれても、傷が浅かったり出血がほとんどなかったりすると、「大したことはないから病院に行かなくてもよいのではないか」と考えてしまう方がいるかもしれません。 しかし、犬に噛まれた場合は基本的に病院を受診することが勧められます。 見た目には軽い傷でも、細菌感染などのリスクによってあとから症状が悪化する可能性があるからです。 ここでは、犬に噛まれた際に考えられる主な感染症と受診の目安を中心に解説します。
2-1.「病院に行かないとどうなる?」:考えられる感染症
犬の口内にはパスツレラ菌やカプノサイトファーガ菌など、多種多様な細菌が存在しており、破傷風や狂犬病のリスクも完全には否定できません。
破傷風や狂犬病は発症すると命に関わる重い病気になります。
なお、日本国内での狂犬病発症例はごく稀ですが、海外渡航時に犬に噛まれる被害に遭えば感染の可能性を考慮する必要があります。
以下は噛まれることにより罹患する可能性のある主要な感染症です。
パスツレラ症
- 概要: 犬・猫の口内に潜むパスツレラ菌による感染症
- 主な症状: 患部の激しい痛みや腫れ、発赤、発熱
- 潜伏期間: 半日~1日程度で症状が出ることが多い
カプノサイトファーガ感染症
- 概要: 犬・猫の唾液に含まれるカプノサイトファーガ・カニモルサス菌などによる感染症
- 主な症状: 発熱、倦怠感、頭痛、まれに敗血症など重篤化するケースも
- 潜伏期間: 数日後(多くは2~3日後)
バルトネラ症(猫ひっかき病)
- 概要: バルトネラ・ヘンセレという菌が原因で発症し、この菌を持つネコノミに寄生され、感染した犬や猫に噛まれたりひっかかれたりすることで二次感染が起こるとされています。
- 主な症状: 噛まれたりひっかかれたりした部分が発熱し、数週間から数か月に及ぶリンパ節の腫脹がみられ、まれに脳症を併発することもあります。
- 潜伏期間: 数日から二週間程度。
破傷風
- 概要: 傷口から破傷風菌が体内に侵入して発症
- 主な症状: 筋肉のこわばり、顎が開きにくくなるなどのけいれん症状から呼吸困難へ
- 潜伏期間: 数日~数週間(最長で約半年)
狂犬病
- 概要: 狂犬病ウイルスに感染した犬に深く咬まれたり、引っ掻かれたりすることで感染し、発症すると致死的になる感染症
- 主な症状: 発熱、興奮、けいれん、のどのけいれんによる水が飲めなくなる症状(恐水症)
- 潜伏期間: 数週間~数年(通常は1~3ヶ月程度)
日本国内で飼育されている犬の場合、狂犬病ワクチンが義務付けられているため発症例はほとんどありません。
ただし、海外で噛まれた場合や、野良犬に噛まれた場合など、明らかにワクチン未接種が疑われるケースでは最優先で医療機関を受診しましょう。
2-2.受診の目安や判断基準
受診の目安としては、傷口の状態に注目する方法があります。
たとえば、出血がいつまでも止まらない、痛みが続いたり強まったりする、傷口が腫れて熱を帯びたり赤みが広がってきたりする、膿のような分泌物が出てくるなどの異常が見られれば、できるだけ早めに医療機関を受診したほうが安全です。
さらに、自身の健康状態が良好ではない場合も受診を急いだほうがよいと考えられます。
高齢者や糖尿病などの基礎疾患がある方、ステロイドを服用するなど免疫機能が低下している方は、軽微な咬傷であっても重症化しやすいといわれています。
また、倦怠感や発熱、頭痛、吐き気、呼吸が苦しくなる、など全身症状が出てきたときは、ただちに医師の判断を仰いでください。
破傷風ワクチンを5年以上接種していない方も注意が必要です。
噛んだ犬の状態として、狂犬病ワクチンの未接種が疑われる場合や野良犬、海外で噛まれた犬であれば、狂犬病や他の感染症のリスクが高くなります。
そのような状況では、渡航先や犬の飼育環境などの情報も含め、医療機関で早めの診察を受けることが重要です。
厚生労働省によると、狂犬病に感染した疑いがある場合には、できるだけ早期に狂犬病ワクチンの接種を受ける必要があるため、速やかに最寄りの保健所または医療機関に相談することを勧めています。
また、狂犬病の予防接種を受けられる医療機関については、検疫所のホームページで紹介しています。
2-3.何科の病院へ行けばいい?
犬に噛まれたときに受診する診療科としては、外科や形成外科がよく挙げられます。
大規模な総合病院だけでなく、地元のクリニックや外科医院でも適切な処置が受けられる場合があります。
傷が深かったり、縫合が必要になったりするときには大きめの医療機関を紹介される可能性もありますが、まずは近くの病院で相談してみるとよいでしょう。
2-4.夜間や休日に噛まれたら?
夜間や休日など、通常の診療時間外に犬に噛まれた場合は、症状が軽く見えても油断できないケースがあります。
出血が止まらなかったり、大きな腫れが見られたりする場合は、そのまま放置すると悪化するリスクがあるため、夜間救急病院に行くことも検討してください。
痛みや腫れが軽度で翌朝まで大きく悪化する兆候がないと感じられれば翌朝ただちに受診する方法もありますが、症状を自己判断するのは難しい面があるため、少しでも重篤化が疑われるなら迷わず夜間救急にかかったほうが安全です。
3.病院以外で「やるべきこと」と手続き

3-1.噛んだ犬の飼い主と連絡先を交換
他人の犬に噛まれた場合は、まず犬の飼い主と連絡先を交換しておきましょう。
治療費や損害賠償が絡む可能性があるうえ、保健所への届け出などでも飼い主が誰か分からないと手続きが進めにくくなります。
もし飼い主が見当たらない場合には、犬の毛色や大きさ、首輪の有無などの特徴をできる範囲で把握しておき、後から保健所に伝えられるようにするとよいでしょう。
3-2.保健所・動物愛護センターへの連絡依頼
自治体によっては、犬が人を噛んだ事案について、その犬の飼い主が二十四時間以内に「咬傷届」あるいは「事故被害届」などを届け出るよう求めている場合があります。
狂犬病予防法の観点から、行政が咬傷事故を把握する必要があるため、飼い主が分かる場合は「保健所や動物愛護センターに連絡してほしい」と依頼しておくことをおすすめします。
犬が適切に狂犬病ワクチンを接種しているかどうかの確認も重要です。
飼い主が連絡をしてくれるか不安なときや飼い主が不明の場合には、自分で保健所や動物愛護センターに問い合わせることもできます。
3-3.警察への連絡と「被害届」
治療費や慰謝料などの請求を検討している場合や、傷が深い大きな咬傷事故になっているときには、警察に連絡して被害届を出す選択肢もあります。
ただし、警察への被害届と保健所へ提出する「届出書」は目的が異なる点に留意してください。
保健所への届出は狂犬病予防の観点から行政が情報収集を行うためのものですが、警察への被害届は刑事上の手続きを進めるために用いられます。
野良犬に噛まれた場合でも、保健所に連絡すれば捕獲に動いてくれる可能性があります。
いずれにしても、まずは自身の身の回りの安全を確保することが大切です。
4.まとめ

犬に噛まれた際は、最初に流水を使って五分以上かけながら丁寧に洗浄し、必要に応じてガーゼなどで圧迫止血を行い、傷を清潔に保護する流れが基本です。 その後は、傷の深さや痛み、出血量だけで判断せず、自身の体調や噛んだ犬の状態などを考慮しながら、できるだけ早めに医療機関を受診するようにしてください。 飼い主が特定できる場合は連絡先を確認し、保健所や動物愛護センターへの届け出や警察への被害届が必要かどうかも合わせて検討するとよいでしょう。 小さな傷だと思っていても感染症のリスクはゼロではなく、特に免疫力が落ちている方や基礎疾患を持つ方は重症化しやすいため注意が必要です。 夜間や休日に噛まれた場合でも、症状が深刻な様子であれば夜間救急を利用して早めに処置を受けるのが安心です。 もしものときに慌てず適切な行動をとれるよう、日頃から対処法や必要な手続きを頭に入れておくと、安全を確保しやすくなります。
【対応の流れ】
- まずは流水で5分以上、患部をしっかり洗浄
- ガーゼなどで圧迫止血し、傷を清潔に保護
- 傷や体調、噛んだ犬の状態を確認し、できるだけ早めに病院を受診
- 飼い主の連絡先や犬の情報をしっかり把握しておく
- 飼い主に保健所や動物愛護センターへの届け出を依頼・必要に応じて警察や保健所へ自ら届け出る
もしものときに慌てず対処できるよう、日頃から病院や保健所などの連絡先を調べておくなどの備えをしておきましょう。












