愛犬の目元につく「目ヤニ」。 健康な犬でも少量なら自然なことですが、色や量、においによっては病気のサインかもしれません。 この記事では、犬の目ヤニが出る主な原因や、正常な目ヤニと異常な目ヤニの見分け方、考えられる病気、そして自宅でできるケアと受診の目安について、獣医学的な知見をもとにわかりやすく解説します。
この記事の監修
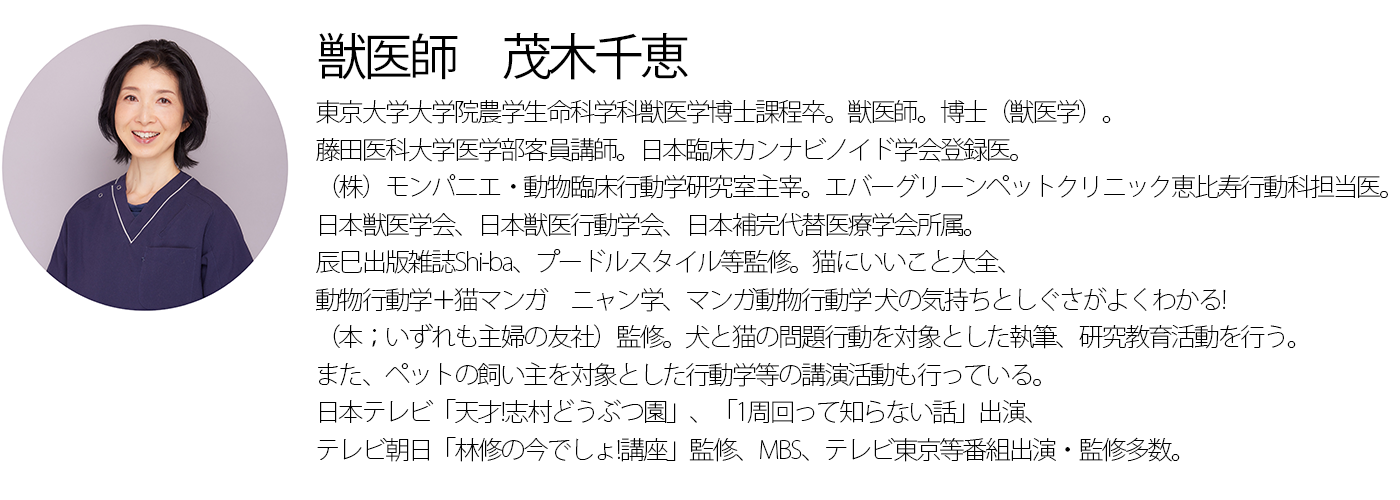
犬の目ヤニが出る主な原因

犬の目ヤニ(眼の分泌物)は、さまざまな原因で発生します。 目は外部刺激から守るため常に涙を分泌し、埃や花粉などを洗い流しています。 その乾燥したものが目ヤニとなって出てくるため、少量の透明〜薄茶色の目ヤニは正常な反応です。 一方、異常に目ヤニが増える背景には以下のような原因が考えられます。
●埃や花粉などの外的刺激
環境中のホコリや花粉、煙などが目に入ると涙が過剰に分泌され、目ヤニが増えることがあります。
一時的な刺激による涙は透明でさらっとしていますが、刺激が続くと慢性的な流涙(涙目)につながります。
関連記事:【獣医師監修】犬にも花粉症がある!?主な症状とこの時期にしたい花粉対策を総まとめ
●ドライアイや加齢による涙腺機能低下
涙の分泌量が減る乾性角結膜炎(ドライアイ)では、目を潤す涙が不足するため眼表面に炎症が起き、黄色や黄緑色の粘り気のある膿のような目ヤニが出ることがあります。
加齢に伴い涙腺やマイボーム腺の機能低下が進行し、ドライアイの発症リスクが高まることが報告されています 。
また、シーズーなど特定の犬種では、免疫介在性KCSの発症率が高いことも知られています。
ドライアイを放置すると角膜潰瘍など重度の目の障害を招きます。
●アレルギー
花粉やハウスダストなどに対するアレルギーによってアレルギー性結膜炎になると目のかゆみや充血、涙・目ヤニの増加を引き起こします。
アレルギー性の目ヤニは比較的サラサラとした透明〜白っぽい分泌物であることが多く、両目に症状が出やすいのが特徴です。
※一方、黄緑色や黄白色の膿状の目ヤニは細菌感染の可能性が高いとされています。
●逆さまつ毛やまぶたの異常
まつ毛が目に向かって生える逆さまつ毛(睫毛乱生;しょうもうらんせい)や、まぶたが内側・外側に巻いてしまう眼瞼内反/外反といった先天的・解剖学的な異常は、角膜を刺激して慢性的な涙・目ヤニの原因になります。
●細菌やウイルスによる感染症
目に病原体が感染すると結膜炎などを起こし、膿のような目ヤニが出ます。
特に片目だけ目ヤニが多い場合や、目ヤニが黄緑色であったり悪臭を伴う場合は、細菌感染が疑われます。
ウイルス感染(例:犬ジステンパーウイルス)でも結膜炎や角膜炎を起こし、分泌物が増えることがあります。
●犬種ごとの体質
犬種によって目の形や構造が異なるため、目ヤニの出やすさにも差があります。
たとえばシーズーやマルチーズなど眼球が大きく突出している犬は瞬きが不完全になりがちで角膜が乾燥しやすい傾向があります。
パグやフレンチブルドッグなど短頭種(鼻ぺちゃの犬)は鼻涙管(涙の排水路)が狭く、涙がうまく排出されず目から溢れやすいです。
またトイプードルなど目の周りの被毛が長い犬は毛が目に入り刺激となって涙や目ヤニが増えることがあります。
以上のように、犬の目ヤニには様々な原因があり、多くは目の刺激や炎症による「涙の増加」か「涙の減少」に起因します。
原因を正しく見極めることで、適切な対処や予防につながります。
正常な目ヤニと異常な目ヤニの見分け方

犬の目ヤニがすべて病気というわけではありません。 健康な犬でも睡眠中に分泌された涙や老廃物が目頭に溜まり、朝に少しカサついた目ヤニがつくことがあります。 重要なのは、普段の目ヤニと比べて「色・量・におい・その他の症状」に異常がないかを観察することです。 以下に正常な目ヤニの特徴と、注意すべき異常サインを示します。
●正常な目ヤニ
量はごく少量で、色は透明〜薄い茶色や淡い赤茶色(乾燥した涙や多少の鉄分による変色)です。
乾くと簡単に取れる程度の固さで、においもほとんどありません。
これは日常的な涙の排出物であり、生理的な範囲内です。
特に朝起きたときに目頭に少し付着する程度のものは心配いらないでしょう。
●異常な目ヤニ
色が黄色や黄緑色、灰白色、または血が混ざる場合は注意が必要です。
こうした変色した目ヤニは、細菌感染や重い炎症のサインであることが多く、しばしば悪臭を伴います。
また粘り気が強くベタベタしている、量が明らかに多く涙が常に溢れている、片目にだけ集中して出ているといった場合も異常の可能性があります。
さらに目ヤニとともに目の充血(白目が赤い)、まぶたの腫れ、目を痒がる素振り(前足でこする等)を伴うときは、何らかの眼疾患を疑うべきサインです。
特に黄緑色の膿状の目ヤニが出ている場合、細菌性の結膜炎など感染症の可能性が高いです。
異常な目ヤニが出ている状態では、目の周囲の皮膚に二次的なトラブルが起きることもあります。
常に湿っていると細菌や真菌が繁殖しやすくなり、目の下の被毛が茶色く変色する「涙やけ」や皮膚炎、においの発生につながります。
実際、目ヤニの多い犬の目の周囲からは、マラセチア菌(酵母菌)の検出率が有意に高かったとの報告もあります(
出典:J Am Vet Med Assoc)。
したがって色や量だけでなく、目ヤニの性状(さらさらか粘着質か)や付着場所、周囲の皮膚状態も併せて観察することが大切です。
ポイント
普段と違う目ヤニが出ていないか日頃からチェックしましょう。
透明で少量の目ヤニは基本的に心配ありませんが、黄色や緑色で粘つく大量の目ヤニ、悪臭を伴う目ヤニは異常のサインです。
犬の目ヤニに潜む病気の可能性
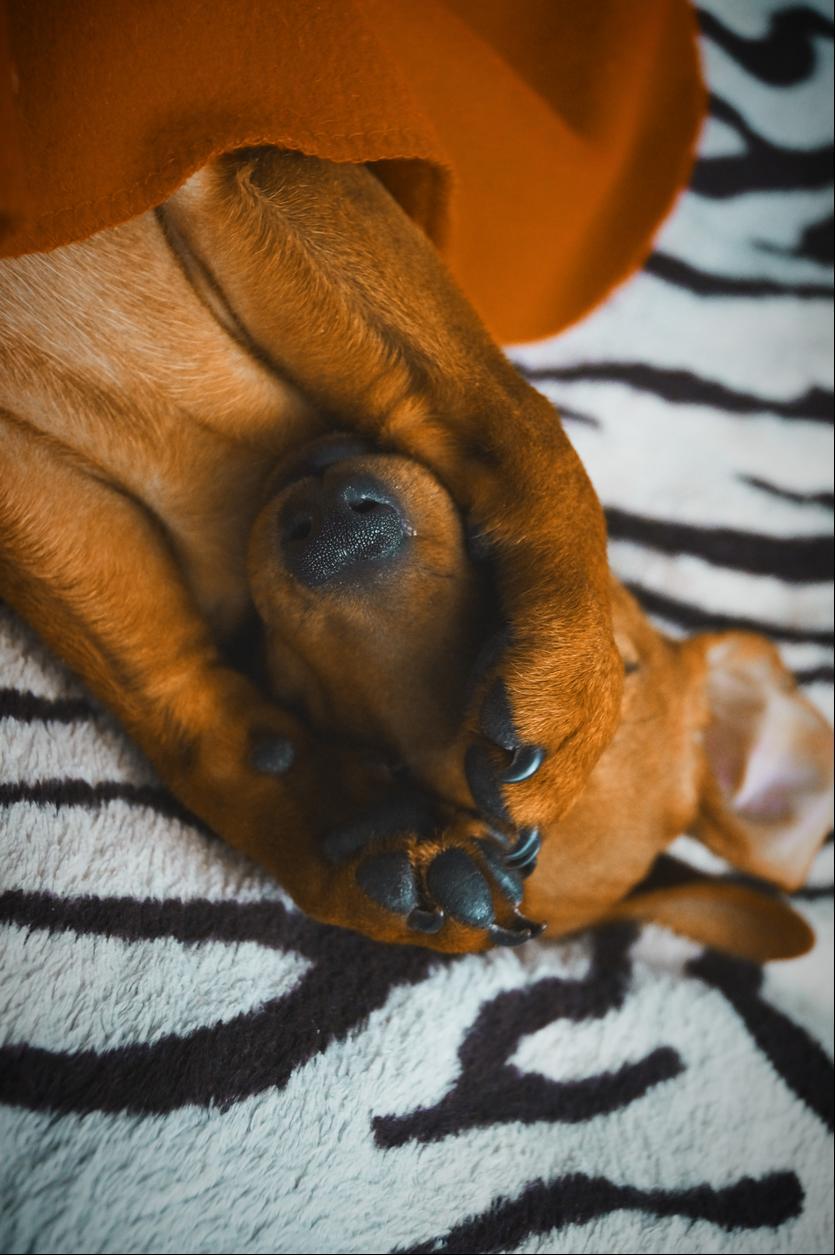
目ヤニの異常は、目自体の病気や全身の疾患の症状として現れることがあります。 ここでは、犬の目ヤニに関連してよく見られる目の病気を紹介します。 それぞれの病気の主な症状や原因を知り、早期発見・治療の参考にしてください。
●結膜炎(けつまくえん)
犬の結膜炎は、目の粘膜の炎症です。
細菌やウイルス、アレルギー、外傷などが原因で、目ヤニ、涙の増加、白目の充血、結膜の腫れ、目を気にするそぶりなどの症状が出ます。
アレルギー性結膜炎は両目に強いかゆみを伴うことが多く、感染性結膜炎(細菌性)は片目から始まり、黄色から緑色の膿性目ヤニが出ることがあります。
点眼薬で治療可能ですが、放置すると角膜への影響や慢性化の恐れがあるため、早期の対処が重要です。
●眼瞼炎(がんけんえん)
瞼(まぶた)やその周囲の皮膚が炎症を起こす病気です。
まぶたが赤く腫れて痛がゆくなり、犬はしきりに目を掻いたり擦ったりします。
炎症が悪化すると透明〜粘液性、時に膿を含む目ヤニが出ることもあります。
原因は様々で、アレルギー(虫刺されや環境アレルゲンも含む)、細菌・真菌感染、寄生虫(ニキビダニなど)、外傷、まぶたの先天異常(眼瞼内反)などです。
眼瞼炎そのものは抗炎症薬や抗生剤で治療しますが、逆さまつ毛や眼瞼内反など根本原因がある場合は外科的治療が必要になるケースもあります。
●角膜炎・角膜潰瘍
犬の角膜(黒目の表面)の損傷や炎症は痛みを伴い、目を細めたり、明るい場所を避けたり、角膜の濁りや充血が見られます。
多くは外傷が原因で、軽度なら表面的な傷で済みますが、重度では激しい痛みを伴います。
短頭種やドライアイの犬はリスクが高いです。
放置すると悪化し、角膜穿孔や失明の恐れがあるため、速やかな獣医の診察が必要です。
治療は通常、抗生物質の点眼や非ステロイド性消炎鎮痛剤が用いられ、エリザベスカラー装着も指示されることがあります。
適切に処置すれば、5〜7日で治癒することが多いです。
●ドライアイ(乾性角結膜炎)
涙の分泌が低下することで角膜や結膜が乾燥し炎症を起こす慢性の疾患で、シーズーやアメリカンコッカー・スパニエルなど特定の犬種に好発します。
目が常に充血して乾燥し、粘っこい黄緑色の目ヤニが大量に出ます。
角膜の光沢喪失、混濁、色素沈着、血管新生も見られることがあります。放置すると、角膜潰瘍や感染症、視力障害のリスクが増大します。
治療には、免疫抑制点眼薬(シクロスポリンなど)と人工涙液による生涯にわたる管理が必要となりますが、早期発見と適切な治療により、症状の改善が期待できます。
●白内障や緑内障
いずれも高齢の犬で目ヤニが増えた時に注意したい疾患です。
白内障は水晶体が白く濁る病気で、初期は目ヤニよりも瞳が白っぽく見えることで知られています。
進行すると視力低下を招きますが、痛みは通常ありません。
緑内障は眼圧が上昇する病気で、強い痛みを伴います。
異常な涙や目ヤニの増加に加え、目をこする、触られるのを嫌がるなどの仕草、眼球突出、白目の充血、角膜の青白い濁りといった症状が見られます。
急激に発症した場合、短時間で失明に至る可能性のある緊急性の高い疾患です。
シニア犬でこれらの症状が見られたら、早急に眼科診療のできる獣医師に相談しましょう。
現在、白内障の根本的な治療法は手術による視覚回復ですが、軽度から中等度の場合は点眼薬で目の健康を維持します。
炎症が強い場合はステロイド点眼も併用します。
犬の緑内障では、まず点眼薬で眼圧を制御し痛みを緩和しますが、進行例や失明後にも眼の痛みが残る場合は外科的治療も選択されます。
●鼻涙管閉塞(びるいかんへいそく)
鼻と目をつなぐ鼻涙管(涙を鼻へ排出する管)が詰まってしまう状態です。
生まれつき管が細い場合や、慢性の結膜炎・鼻炎などで管が炎症を起こし狭くなることで発生します。
涙の排出路が塞がれるため、常に涙が目から溢れ出て目ヤニも増加します。
いわゆる「流涙症(涙やけ)」の一因であり、目の下の被毛が茶色く染まったり皮膚炎になることがあります。
治療は全身麻酔下で管の洗浄や通水を行う処置が一般的ですが、再発する場合もあります。
短頭種や小型犬に多く見られるため、これらの犬では日頃から目の周りを清潔に保つことで症状の悪化を防ぐことが大切です。
以上のように、一口に目ヤニと言っても背後に潜む病気は多岐にわたります。
「単なる目ヤニ」と侮らず、色や状態によっては重大な疾患の初期症状である可能性も念頭に置いてください。
早期発見・治療のためには、日頃から愛犬の目の状態をよく観察し、少しでも異常を感じたら専門家に相談することが重要です。
自宅でできるケアと病院に行く目安

異常な目ヤニに気づいた際は早めの受診が望ましいですが、軽度の場合や日常ケアとして飼い主が自宅でできる目のケアもあります。 正しいケア方法で愛犬の目を清潔に保ち、トラブルを予防しましょう。 また、どのような状態になったら病院に行くべきかの目安も示します。
●目ヤニの正しい拭き取り方
目ヤニを見つけたら、優しく拭き取って清潔にすることが基本です。
乾いた目ヤニは無理に剥がさず、まずぬるま湯で湿らせたガーゼやコットンで目頭を軽く押さえて柔らかくします。
そしてふやけた目ヤニを目頭から外側に向かってそっと拭き取りましょう。
ゴシゴシ擦ると眼球や皮膚を傷つける恐れがあるためNGです。
人間用のティッシュペーパーは乾燥していて目に繊維が残りやすいため、できれば湿らせたガーゼやコットンの使用がおすすめです。
市販のペット用アイケア用品(アイクリーナーや専用シート)があればそれを使っても構いません。
特に白い被毛の犬種で目の下が涙やけしやすい場合、毎日、目の周りを拭いてあげると茶色い着色や臭いの防止になります。
※ただし目の表面(角膜)を直接擦らないよう、あくまで目の周囲の毛や皮膚についた分泌物を拭うイメージで行ってください。
【ぷにわんモールおすすめ商品】
Love Quality 涙やけとるワン 犬用 60包(1包2枚入り)

●目のケアでやってはいけないこと(NG行為)
上記の通り、乾いたティッシュで強く擦ることは角膜を傷つける原因になります。
自己判断で人間用の目薬を使用することは絶対に避けてください。
犬にとって有害な成分が含まれている可能性があり、症状を悪化させる危険性があります。
必ず獣医師の指示に従い、犬専用の点眼薬を使用してください。
また、目ヤニがひどい場合でも、シャンプーや石鹸で目の周りを洗うのは避けるべきです。
シャンプーの成分が目に入ると刺激となり、炎症を悪化させる原因となります。
●日常的に心がけたい予防・清潔管理
目ヤニや涙やけ予防には日々のケアが重要です。
目ヤニ体質やアレルギーを持つ犬は特に、以下の点に注意して環境を整えましょう。
- こまめな掃除: ハウスダストを減らし、症状を緩和します。
- 花粉対策: 散歩後、顔周りを濡れタオルで拭き花粉を取り除きます。
- 空気清浄機の活用: 室内への設置が有効です。
- 定期的なシャンプー・グルーミング: 顔周りを清潔に保ちます。
- 目の周りの被毛カット: 毛の刺激を防ぎます。
- 短頭種のシワのお手入れ: シワの間も清潔に拭きます。
これらの継続的なケアで、目ヤニや涙やけを予防できます。
●受診の目安
次のような状況が見られたら、早めに動物病院で診察を受けることをお勧めします。
- 目ヤニの色が黄色・緑色、または血液が混ざっている(感染症や眼球の損傷の疑い)
- 目ヤニの量が急に増えた、または常に涙と目ヤニがあふれている(異物混入や涙管閉塞、急性の炎症の可能性)
- 目の充血やまぶたの腫れ、目を痒がる様子を伴う(痛みや炎症が強いサイン)
- 目ヤニが片方の目にだけ大量に出ている(外傷など外因性の可能性)
- 数日ケアしても改善せず長引いている(自己治癒が見込めず獣医師による治療が必要)
これらの症状は、結膜炎・角膜潰瘍・緑内障など進行すると視力障害につながる病気の兆候かもしれません。
「おかしいな」と感じた段階で早めに対処することが、愛犬の目の健康と視力を守ることに繋がります。
まとめ

犬の目ヤニは日常的に見られる現象ですが、その色や量、状態によっては病気のサインになり得ます。 正常な目ヤニと異常な目ヤニの違いを知り、異変に気付いたら早めに動物病院を受診することが大切です。 日頃から目の周りを清潔に保ち、適切なケアを行うことで多くの目のトラブルは予防・早期発見できます。 適切な処置とケアで、愛犬の目の健康と快適な視界を守ってあげましょう。












