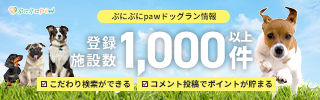「犬も花粉症になるのだろうか?」と思われる飼い主さんは少なくありません。 実際、犬にも花粉症に似たアレルギー症状が起こることは多く、鼻水やくしゃみだけでなく、皮膚がかゆくなる、赤みやブツブツした発疹が見られるなど、人間とは少し異なる症状が出るのが特徴です。 本記事では、犬の花粉症の主な症状から、治療や検査の受け方、そして飼い主さんが日々できる対策までを詳しく解説します。 特に「いつものかゆみ程度だと思って放置していたら、実は重篤な病気だった」という可能性もあるため、自己判断の危険性についても触れています。 愛犬のかゆみや鼻水などに悩む飼い主さんが、日々のケアや病院への受診を検討するきっかけになれば幸いです。 ぜひ最後までお読みいただき、愛犬に快適な生活を送ってもらうためのヒントを見つけてください。
この記事の監修
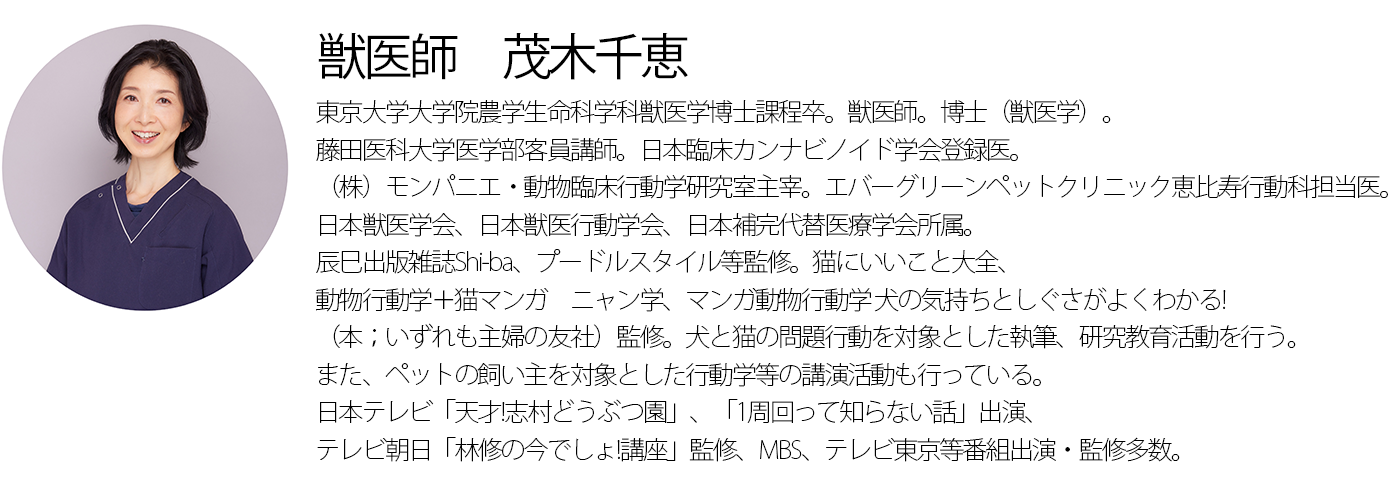
1.犬にも花粉症は「ある」
犬にも花粉症があるって本当?
犬も私たち人間と同様に花粉が原因でアレルギー反応を起こすことがあります。
ただし、獣医師による正式な診断名として「花粉症」という言葉が使われることはあまりなく、症状や病態に応じて「アトピー性皮膚炎」や「アレルギー性皮膚炎」などと呼ばれることが一般的です。
花粉の種類と時期
日本ではスギやヒノキの花粉症が有名ですが、犬の場合はブタクサ(キク科)などの雑草によるアレルギーが比較的多いとされています。
以下は、日本における代表的な花粉飛散スケジュールの一例です(地域によって差があります)。
| 月 | 主な花粉 |
| 1~3月 | スギ、ヒノキ |
| 4~6月 | イネ科(カモガヤなど) |
| 7~8月 | イネ科、キク科(ブタクサなど) ※地域により変動 |
| 9~10月 | ブタクサ、ヨモギなどキク科の雑草 |
| 11~12月 | スギ(地域によっては11月頃から飛散開始) |
なかでもブタクサは犬のアレルゲンとなることが多く、河川敷や土手、公園の草むらなどでよく見かける雑草です。
散歩コースによっては犬が日常的に接触しやすいため、注意が必要です。
花粉症の発症年齢とアレルギーを起こしやすい犬種
発症年齢
生後6か月以降であれば発症する可能性はありますが、特に1~3歳の時期に初めて症状が現れるケースが多いとされています。
アレルギーやアトピーを起こしやすい犬種
- 柴犬
- ボストン・テリア
- スコティッシュ・テリア
- ウエスト・ハイランド・ホワイトテリア
- ピット・ブル・テリア
- フレンチ・ブルドッグ
- イングリッシュ・ブルドッグ
- パグ
- シーズー
- ゴールデン・レトリバー
- ラブラドール・レトリバー
- ジャーマン・シェパード
- コッカー・スパニエル
- ダルメシアン
- ボクサー
- セッター
また、アメリカ獣医師会の発表によると、犬の花粉症は増加傾向にあるといわれています。
日本でも同様に、環境やライフスタイルの変化などから、花粉症にかかる犬が増えている可能性は高いでしょう。
2.犬の花粉症の主な症状

犬の花粉症は、人間のようにくしゃみや鼻水ばかりが目立つのではなく、皮膚のかゆみや発疹など皮膚症状が中心になる点が大きな特徴です。 以下に多い順で主な症状をまとめました。
皮膚のかゆみや赤み、発疹(ブツブツ)
・足先、顔、耳、前脚、腹部、足や尾の付け根に症状が出やすい。
家具や床に顔をこすりつける、皮膚を噛んだり舐めたり掻いたりする。
・耳の炎症(外耳炎)
頭をしきりに振る、耳の内側をかゆがる、においや耳垢が気になる。
・目のかゆみ、充血、目やに
目を頻繁にこする、涙が増える、目やにが多くなる。
・鼻水、くしゃみ
透明でサラサラした鼻水が出ることもあるが、皮膚症状に比べると頻度はやや低い。
・季節性(特定の時期だけ悪化する)
花粉症は、該当する花粉の飛散時期だけ症状が強くなる(季節性)という特徴があります。
春だけ発症する、秋になると悪化するといった場合は、犬の花粉症を疑う一つの目安になります。
花粉症と似た別の病気に注意
花粉症と思われる症状でも、犬の皮膚のかゆみにはほかの病気が潜んでいる可能性があります。
たとえば、ノミやダニなどの寄生虫感染、あるいは甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症などのホルモン異常が原因となり、皮膚バリア機能の低下や細菌感染を招くことがあります。
また、皮膚肥満細胞腫や皮膚型リンパ腫など、皮膚に発生するがんでもかゆみが生じる場合があります。
また、目の症状が認められる場合、ぶどう膜炎や角膜潰瘍などの眼疾患が原因の場合もあります。
これらの病気は放置すると重症化し、犬の命に関わる場合もあります。
自己判断は非常に危険ですので、愛犬に気になる症状があるなら、まずは動物病院で検査を受けましょう。
【コラム】犬の花粉症を憎悪させる要因
犬の花粉症は「花粉との接触量」をできるだけ減らすことが大切ですが、加えて注意したいのは、症状を悪化させる要因への対策です。
たとえば、皮膚のバリア機能が低下している犬は花粉の刺激に弱く、かゆみや炎症がいっそう強くなりがちです。
これは、シャンプーの頻度やケア方法が合っていない場合や、栄養バランスの乱れ、もともと皮膚疾患を抱えているといった状況によって引き起こされます。
また、河川敷や土手、草むらなど花粉の多い場所を散歩コースに選んでいると、被毛や皮膚に大量の花粉が付着して症状が増悪しやすくなります。
空気の乾燥も見逃せないポイントで、被毛に静電気が生じると花粉を引き寄せやすくなるため、特に長毛の犬やブラッシング不足の犬は十分な注意が必要です。
さらに、屋外から持ち込んだ花粉が室内に残留しやすい環境では、掃除や換気を怠るほど犬が繰り返し花粉に触れてしまい、症状が長引く原因になります。
加えて、強いストレスや体調不良があると免疫力が低下し、花粉への反応が過敏になるケースもあるため、犬の健康状態やメンタル面の管理も重要です。
ほかのアレルゲン(ノミ、ハウスダスト、ダニなど)と併発している場合は、花粉と相乗的に作用してより重度のアレルギー症状を引き起こすことが考えられます。
これらの要因を回避、あるいは軽減するためには、日頃から皮膚ケアや散歩コースの工夫を行い、室内のこまめな掃除と換気を徹底するとともに、犬のストレスや体調不良のサインを見逃さないよう注意することが大切です。
3.犬の花粉症治療と検査費用

3-1.犬の花粉症は治療が必要?
かゆみや皮膚炎、鼻水・くしゃみなどの症状が出ている場合は、必ず動物病院で診察を受けましょう。
軽い症状に思えても、犬自身にとっては慢性的なストレスや二次感染の原因になります。
また、「本当に花粉が原因か」を調べるためにも、早めの受診が大切です。
花粉症かと思いきや別の病気だった、というケースも少なくありません。
3-2.犬が花粉症かどうか判断する方法(アレルギー検査)
・血液検査
犬に多いアレルギー原因(スギ、ヒノキ、イネ科、ブタクサなど)を複数項目まとめて調べられます。
・皮膚検査や除去試験
実際に皮膚にアレルギーの原因物質を少量だけ塗りつけて、赤くなるかどうか反応をみたり、原因物質を食事や生活環境から除去した生活を一定期間送ることで症状の変化を確かめる方法もあります。
3-3.費用の目安
検査方法や病院によって差はありますが、血液検査の場合1万円~3万円程度が一般的な目安です。
ほかに診察料や再診料、投薬費用などもかかることがあるため、詳しくは受診前に動物病院で確認してみてください。
4.犬の花粉症対策と予防法

ここからは、飼い主さんが日常生活で取り組める具体的な花粉症対策を6つ紹介します。 【対策①】花粉を避ける(散歩の時間帯を変える) 【対策②】散歩中に花粉を付着させない 【対策③】花粉を室内に持ち込まない(花粉を落とす) 【対策④】花粉を広げない 【対策⑤】花粉から皮膚を守る(保湿ケア) 【対策⑥】「交差反応」が考えられる野菜や果物を与えない
【対策①】花粉を避ける(散歩の時間帯を変える)
飛散量が多いお昼前後や夕方(18時前後)の時間帯を避けて、早朝や夜遅めに散歩をする方法があります。
雨上がりの翌日や風が強い日は花粉が大量に舞いやすいので、短めの散歩にしたり、ルートを変えたりするなどの工夫をしましょう。
【対策②】散歩中に花粉を付着させない
静電気防止加工が施された犬用ウェアを選ぶと被毛に花粉がつきにくくなります。
地面に直接触れる足先は花粉がつきやすい部位なので、犬用シューズ(靴やソックス型のもの)を履くと帰宅後のケアがグッと楽になります。
【対策③】花粉を室内に持ち込まない(花粉を落とす)
散歩後に家の中に入る前に十分ブラッシングし、被毛に付着した花粉を落とします。
濡れタオルやウェットシートで足裏や顔、腹部などを拭くのも効果的です。
飼い主さんの髪や衣類にも花粉が付着しているので、玄関先で花粉を払い落としてから入るのがおすすめです。
【対策④】花粉を広げない
日中を過ごすリビングなどには、花粉捕集性能の高い空気清浄機を使い、適度な湿度を保つことで花粉の舞い上がりを抑えましょう。
【対策⑤】花粉から皮膚を守る(保湿ケア)
被毛や皮膚についた花粉を洗い流す回数を増やすことを検討します。
ただし、皮膚トラブルがある場合は獣医師に相談の上、処方されるシャンプーを使いましょう。
シャンプー後には必ず犬用保湿クリームを使い、足先や腹部など乾燥しやすい部位をケアしましょう。
【対策⑥】「交差反応」が考えられる野菜や果物を与えない
交差反応とは、ある花粉に対するアレルギーをもつ場合、食する部分の構成成分が似ている果物や野菜でもアレルギー症状が出る可能性がある現象です。
花粉ごとの交差反応例
| カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ) | リンゴ、サクランボ、モモ、ナシ、ビワ、ヘーゼルナッツ、大豆、ピーナッツ、ニンジン、セロリ など |
| ヒノキ科(スギ、ヒノキ) | トマト など |
| イネ科、ブタクサ、ヨモギ(草本花粉) | メロン、スイカ、キュウリ、ズッキーニ、トマト、オレンジ、バナナ、マンゴー、セロリ、ニンジン、ピーナッツ など |
※草本花粉:樹木ではなく雑草の花粉のこと
犬によって実際に症状が出るかは個体差がありますが、既に特定の花粉アレルギーが確認されている場合は注意しましょう。
5.まとめ

この記事では、次のような内容を解説しました。 1.犬にも花粉症(アレルギー症状)がある スギ、ヒノキ、イネ科、ブタクサなど、さまざまな植物の花粉が原因となり得ます。 2.犬の花粉症の代表的な症状 鼻水やくしゃみよりも、皮膚のかゆみや赤み、発疹が多い。 【コラム】犬の花粉症を悪化させる要因 皮膚のバリア機能低下、静電気による花粉付着、室内環境への花粉残留、ストレスなど。 3.犬の花粉症治療と検査費用 似た症状でも別の病気の可能性があるため、早めの検査が大切。 4.飼い主さんができる花粉症対策の一覧 ・散歩の時間帯やコースを変える ・犬用ウェアやシューズで被毛・足裏への付着を抑える ・帰宅後のブラッシング・拭き取りで花粉を落とす ・室内の掃除、空気清浄機・加湿器で花粉を広げない ・シャンプーや保湿ケアで皮膚バリアを保つ ・交差反応が疑われる野菜や果物は控える さらに、ぷにぷにpawでは、犬の花粉症対策に役立つアイテムを数多く紹介しています。
花粉症は、対策を怠ると犬にとって大きなストレスや健康被害につながります。
「あのときもっと早く病院に行っておけばよかった…」
「対策をきちんとしてあげられなかった…」
と後悔する前に、早期受診と日頃の予防ケアを徹底してあげましょう。