愛犬がそわそわと落ち着かずウロウロしていると、「どこか具合が悪いのでは?」「ストレスを感じているのかも?」と心配になりますよね。 犬が落ち着かない行動を見せる背景には、環境や気持ちの問題から体の不調、さらには高齢犬の場合は認知症(認知機能不全症候群)の兆候まで、さまざまな原因が考えられます。 本記事では、犬が落ち着きなくなるときに見られる症状やサイン、考えられる原因と病気について、最新の獣医学知見をもとにやさしく解説します。 大切な愛犬の異変に気付いたとき、自己判断に頼らず適切に対処できるよう一緒に考えていきましょう。
この記事の監修
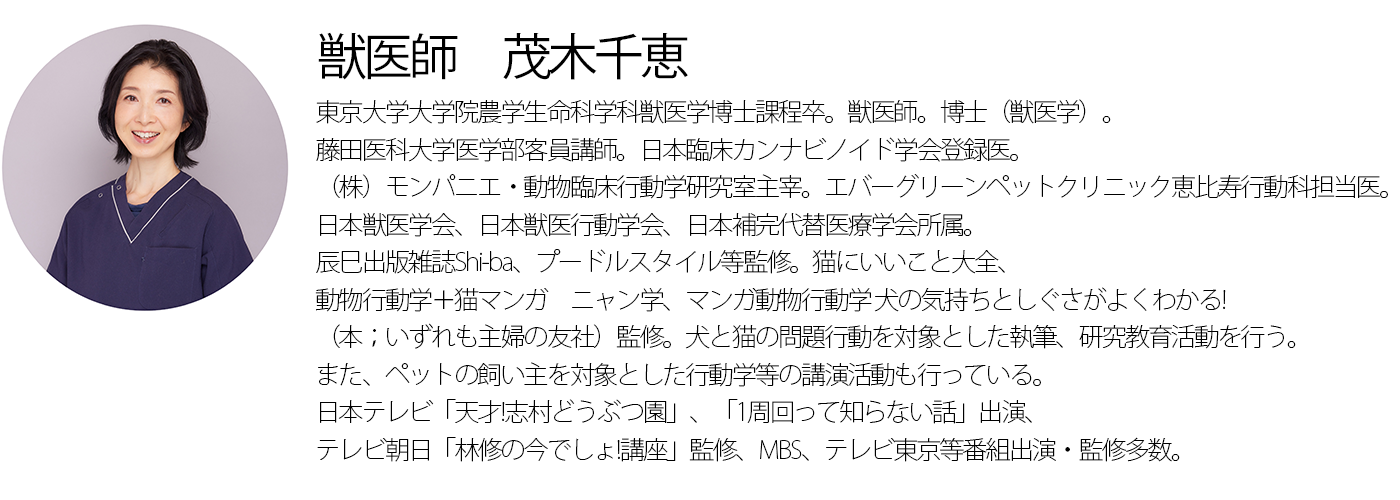
落ち着かない犬に見られる主なサイン(症状)

まず、「犬が落ち着かない」とは具体的にどのような様子でしょうか。 一般的に次のような行動が見られます。
●絶えずウロウロと歩き回る・徘徊する
部屋の中を行ったり来たりして座ったり伏せたりせず、常に動き回っている。
特に夜間、家族が寝静まった後に家の中を歩き回ることもあります。
●ソワソワして座らない・伏せない
落ち着きがなく、その場で長く留まらずに姿勢を変えたり場所を移動したりします。
寝床に入ってもすぐ出てきてしまい、なかなか寝付けない様子も見られます。
●頻繁に周囲を気にする・要求行動が増える
キョロキョロと周囲を見回したり、飼い主さんの後をついて回って落ち着かないこともあります。
必要以上に飼い主さんに甘えたり吠えたりするケースもあるでしょう。
●夜鳴き・遠吠えやクンクンと鳴く
夜中に理由なく鳴き続ける、あるいは飼い主さんの姿が見えなくなると不安で吠えるなど、特に夜間に不安そうな鳴き声をあげるのも落ち着きのなさの一種です。
●粗相(トイレの失敗)
普段はトイレを失敗しない成犬が、部屋の中でおしっこやうんちをしてしまうことがあります。
落ち着きなくウロウロしている途中でしてしまう、トイレの場所を間違える、といった様子が見られるかもしれません。
以上のようなサインがいくつも重なって見られる場合、単なる一時的な興奮やクセではなく、何らかの異変が起きているサインと考えましょう。
特に高齢の犬でこれらの症状が増えてきた場合は、認知機能の低下による行動変化の可能性があります。
次のセクションで原因を詳しく見てみましょう。
落ち着きがない行動の主な原因

犬が落ち着きを失ってしまう原因は、大きく分けて心理的な要因と身体的な要因があります。 以下に主な原因を挙げます。
●環境や心因性のストレス・不安
環境の変化(引っ越しや模様替え)や雷雨、花火などに驚いて不安になると、犬は落ち着かずウロウロすることがあります。
分離不安のある犬では、飼い主さんと離れている間にソワソワと探し回ったり、不安で鳴き続けたりすることがあります。
若い犬でも運動不足や退屈で落ち着きがなくなる場合があります。
●加齢に伴う感覚機能の低下
高齢になると視力や聴力が低下し、飼い主さんの存在に気づきにくくなることがあります。
その結果、不安や混乱から夜間に落ち着かず徘徊したり鳴いたりすることがあります。
●痛みや体の不調
痛みは犬の落ち着きを奪う大きな原因です。
関節炎やケガ、内臓疾患による腹痛など、慢性的な痛みや不快感があると、犬は苦痛で寝付けずに頻繁に体勢を変えたり歩き回ったりすることがあります。
●脳や神経の問題
脳の疾患(脳腫瘍やてんかん発作など)でも行動の変化が現れることがあります。
発作の前兆で落ち着きなく徘徊したり、同じ所をぐるぐる回る行動が続いたりする場合もあります。
●老年性の認知機能低下
高齢犬では認知症(認知機能不全症候群)の初期に落ち着きのなさや奇妙な行動が出ることがあります。
夜間の徘徊や昼夜逆転、目的もなく歩き回る・鳴き続ける、といった症状が現れることがあります。
以上のように、「落ち着きがない」背景には様々な要因があります。
若い犬では環境やストレスによる一過性のケースもありますが、高齢犬の場合は痛みなどの体調不良や認知機能の低下が関与していることが多いです。
気になる症状が続く場合は早めに動物病院で相談しましょう。
愛犬が落ち着かないときに考えられる病気
上で挙げた原因に関連して、犬の落ち着かない行動に結びつく代表的な病気や異常には次のようなものがあります。
●認知機能不全症候群(いわゆる犬の認知症)
シニア犬で夜鳴き・徘徊・トイレの失敗などを引き起こす代表的な病因です。
ゆっくり進行する脳の変性疾患で、記憶障害や見当識障害(迷子になる)、睡眠リズムの乱れ、飼い主との関わり方の変化など行動面の異常が現れます。
●不安障害(分離不安、恐怖症など)
飼い主さんと離れると極度の不安からパニックになったり、雷や花火など特定の刺激に怯えて落ち着きを失う場合があります。
若い犬でも見られますが、高齢になり視覚・聴覚が衰えると不安を感じやすくなり発症することもあります。
●慢性疼痛(関節炎、歯の痛みなど)
慢性的な痛みは犬の行動に大きく影響します。
例えば変形性関節症(関節炎)による関節痛、重度の歯周病による歯痛、癌による痛みなどがあると、犬は寝ていても痛みで目が覚めて歩き回ったり、苦痛から落ち着きを失ったりします。
●内分泌疾患(ホルモンの病気)
ホルモンバランスの乱れによる疾患も行動変化を招くことがあります。
犬ではクッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)になると多飲多尿やパンティング(浅速い呼吸)が増え、夜間に落ち着かなくなることがあります。
●脳・神経の病気
脳腫瘍は、病変部位が脳を圧迫することにより認知症に似た症状(同じ方向への旋回、視力障害による不安・混乱など)を引き起こすことがあります。
またてんかんの部分発作でも落ち着きなく歩き回る、一点を見つめて鳴き続ける等の行動が出ることがありますが、いずれも神経学的検査や画像検査を行って診断します。
●心疾患・呼吸器疾患
心臓病によるうっ血性心不全や呼吸器の病気で夜間に呼吸が苦しくなると、横になって休むことができなくなり、起き上がって徘徊したり落ち着かない様子を示すことがあります。
以上のように、落ち着きのなさは様々な疾患のサインとなりえます。
症状が進行している場合は、一刻も早く受診して検査を受けることをおすすめします。
高齢犬に多い認知症(認知機能不全症候群)とは

犬の認知機能不全症候群(Canine Cognitive Dysfunction; CCD)は、人でいうアルツハイマー型認知症に類似した、高齢犬に現れる神経変性疾患です。 脳の老化に伴い神経細胞が徐々に機能不全に陥り、認知能力や記憶・学習能力が低下していく進行性の病気です。 犬の認知症は決して珍しい病気ではありません。 アメリカの調査によれば、11~12歳の犬の約28%に何らかの認知症徴候が見られ、15~16歳では約68%に達すると報告されています。 つまり15歳を超える犬では半数以上に認知機能低下の症状が出現している計算です。 認知症は早期発見・早期対応が鍵となる病気です。 進行を完全に止める治療法はないものの、早めに気づいてケアを開始すれば症状の進行を遅らせたり生活の質を維持したりすることが可能とされています。
認知症の犬に見られる症状サイン
犬の認知症の典型的な症状は頭文字をとって「DISHAA」と表現されることがあります(Disorientation〈見当識障害〉、Interaction〈交流の変化〉、Sleep-wake cycle〈睡眠周期の変化〉、House-soiling〈排泄失敗〉、Altered activity〈活動性の変化〉、Anxiety〈不安の増加〉)。
実際によく報告される症状としては、昼間に寝て夜に落ち着きなく徘徊する、家族に対する反応や興味が薄れる、家の中で迷子になる・出られなくなる、トイレを失敗する、理由もなく吠え続ける、活動量が減るまたは落ち着きなく歩き回る、以前できた号令を忘れる等が挙げられます。
初期には軽度な症状でも、複数の兆候が重なって見られる場合には認知症の可能性が高まります。
進行すると家族を認識できず他人行儀に吠える、昼間も声をかけても振り向かない、排泄をする場所を忘れて失敗するといった変化が顕著になり、多くの飼い主さんが異変に気付きます。
この段階で夜鳴き(夜中に理由なく吠える)が激しくなり、動物病院を受診するケースが増えるようです。
現在の獣医学ではいったん発症した認知症を完治させることは難しいですが、進行を遅らせたり症状を緩和するための様々なケアや治療法(環境調整、食事療法、サプリメント、内服薬など)が存在し、有効であることが確認されています。
特に抗酸化成分や中鎖脂肪酸を強化した療法食と環境エンリッチメント(適度な運動やパズル玩具などによる脳刺激)の組み合わせが症状の改善に効果的だったとの報告もあります。
不安が強い場合は抗不安薬の併用も検討されます。
動物病院を受診するべきタイミングとポイント

愛犬の様子がおかしいと感じたら、「早めの受診」が基本です。 犬の落ち着きのなさが一過性でなく続く場合、迷わず動物病院に相談しましょう。 特に以下のような場合は受診の目安になります。
- 落ち着かない様子が丸一日以上続いている、または頻繁に繰り返す場合。普段と明らかに様子が違う行動が続くときは何らかの異常のサインと考えられます。
- 高齢犬で上記「認知症のサイン」が複数みられる場合。
- 震え、ふらつき、呼吸が荒い、嘔吐下痢、けいれん発作などを伴う場合。緊急性の高い疾患や痛みが疑われますので、できるだけ速やかに診察を受けてください。
- 環境要因やストレスで説明がつかない急な落ち着きのなさは、痛みや内臓疾患、脳の問題など専門的検査でないとわからない原因が潜んでいることがあります。
受診時には、いつ頃からどんな様子がみられるかを具体的にメモして伝えると診断の助けになります。
スマホで愛犬の様子を動画撮影して見せるのも有効です。
動物病院では、問診・身体検査に加えて血液検査や尿検査を行い、痛みの原因や内臓の不調、ホルモン異常の有無を調べます。
必要に応じて神経学的検査やMRI/CT検査で脳の状態を確認し、他の病気がないか徹底的にチェックしたうえで診断されます。
自宅でできる愛犬を落ち着かせる工夫

動物病院で原因に応じた治療やアドバイスを受けたら、ご自宅でのケアも愛犬の安眠・安心に大きな効果を発揮します。 以下に、落ち着かない愛犬のために飼い主さんができる工夫をいくつか紹介します。
●環境を整えて安心できる寝床を用意する
寝る場所は静かで落ち着けるスペースにしましょう。
暗闇を怖がる子には足元灯や豆電球でほのかな明かりをつけてあげると安心することがあります。
●昼間の過ごし方を見直し適度に刺激を与える
日中に適度な運動や遊びを取り入れてしっかり身体を動かすことで、夜にぐっすり眠りやすくなります。
例えば軽い散歩や穏やかな遊びで適度に疲れさせ、夕方以降は徐々に照明を落としてリラックスタイムに移行しましょう。
●生活リズムを整える
毎日ご飯や散歩の時間を規則正しくすることで、犬の生体リズムを整えます。
高齢犬では朝日を浴びる散歩や朝の活動で体内時計にメリハリをつけ、夜は自然に眠気が来るよう促しましょう。
●夜間のトイレ対策をしておく
高齢でトイレを失敗しがちな子や、夜中にソワソワ動いて粗相してしまう子には、寝る前にトイレをもう一度促す習慣をつけましょう。
●かまいすぎず穏やかに見守る
愛犬が落ち着きなくしていると心配になりますが、過度に構いすぎてしまうと興奮を助長する場合もあります。
基本的には危険がないよう環境を整えた上で、飼い主さんは穏やかな態度で見守ることが大切です。
撫でたり声をかけたりする際も落ち着いたトーンで接し、不安を和らげるようなスキンシップを心がけましょう。
●必要なら獣医師に相談しつつお薬やサプリを活用
不安や夜間の興奮がひどい場合、獣医師が鎮静効果のある抗不安薬や睡眠導入剤を処方してくれることがあります。
かかりつけの獣医師に相談し、ホームケアの一助として処方してもらうと安心です。
以上のような工夫によって、犬の不安や混乱を和らげ、夜間も穏やかに過ごせる手助けができるでしょう。
特に認知症の犬では「安心できる環境づくり」が症状緩和のポイントになります。
無理にやめさせようと叱るより、原因に寄り添った対策で愛犬の気持ちを落ち着かせてあげてください。
まとめ:まずは原因を正しく知り、早めのケアで愛犬に穏やかな毎日を

犬が落ち着かない様子を見せるとき、その裏には不安やストレス、痛み、加齢による変化など様々な原因が潜んでいます。 一見ただソワソワしているだけに見えても、高齢犬であれば認知症の初期兆候の可能性がありますし、若い犬でも思わぬ体調不良が隠れていることもあります。 幸い、現在の獣医療では犬の認知症を含め多くの場合でサポートする方法が用意されています。愛犬の行動に「いつもと違う」サインを感じたら、「性格だから」とか「年だから仕方ない」などと思い込まず、ぜひ早めに獣医師に相談してください。 専門家の力を借りながら原因を見極め、愛犬に合ったケアを続けることで、きっとまた穏やかな笑顔が戻ってくるはずです。 飼い主さんと愛犬が共に安らかな毎日を送れるよう、できる限りのサポートをしてあげてください。












