「レプトスピラ症」という病名を聞いたことがありますか? この病気は、単に犬が罹る感染症というだけではありません。 実は、犬から人へ、そして人から犬へと感染する可能性のある「人獣共通感染症」であり、ご家族全員の健康に関わる重要な病気です。 原因となる細菌は、雨上がりの水たまりや公園の湿った土の中など、私たちの身近な環境に潜んでいます。 特に、川遊びやキャンプなどアウトドア活動に良く行く犬はもちろん、最近では都市部での感染例も増えており、「うちの子は外で活発に遊ばないから大丈夫」とは言い切れない状況です。 愛犬と家族の健康を守るため、レプトスピラ症について知ることは不可欠です。獣医師がその正体、症状、感染経路、予防法を分かりやすく解説します。
この記事の監修
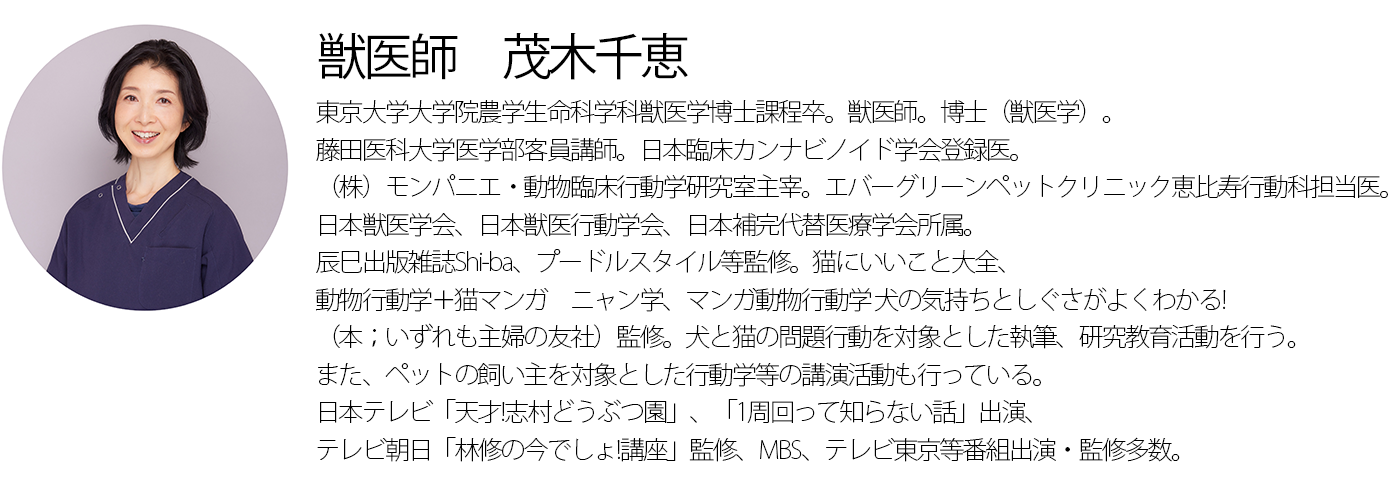
犬のレプトスピラ症とは

犬のレプトスピラ症は、レプトスピラ属の細菌に感染することによって引き起こされる病気です。 この病気は世界中で発生しており、犬だけでなく、人やネズミ、家畜など多くの哺乳類に感染します。
レプトスピラ菌の特徴
原因となるレプトスピラ菌は、コルクの栓抜きのような、細長いらせん状の形をしたスピロヘータという細菌の仲間です。
この菌の最大の特徴は、水中や湿った土壌といった、暖かく湿った環境で数週間から数ヶ月もの間、生き延びることができる点です。
この生存能力の高さが、身近な環境に感染のリスクが潜む理由となっています。
また、レプトスピラ菌には300種類以上の血清型(菌のタイプ)が存在することが知られており、この多様性がワクチンの効果にも関係してきます。
6種以下の混合ワクチンを接種していてレプトスピラ症に対応していない場合は、かかりつけの獣医師に相談し、予防注射のメリット・デメリット、抗体保持期間、費用などの詳細な説明を受けた上で、追加接種を検討することをお勧めします。
日本での発生状況
かつてレプトスピラ症は、沖縄や九州といった温暖で湿潤な地域での発生が多いとされていました。
国立感染症研究所が発表している、人でも感染症データを見ても、沖縄県での報告が最も多いことが示されています。
季節的には、気温と湿度が高くなる梅雨時から、台風シーズンでもある夏から秋(7月~10月)にかけて感染のピークを迎えます。
しかし、近年この状況は変化しています。
これまで安全と思われていた地域でも感染リスクが現実のものとなっているのです。
特に注目すべきは、近年関東地方でレプトスピラ症の発生が報告されていることです。
2025年には、千葉県船橋市で2例、市原市で1例、神奈川県藤沢市で1例の犬の感染が確認されています。
これらの事例は、レプトスピラ症がもはや特定の地域の風土病ではなく、日本の多くの地域、特に都市部やその近郊に住む犬にとっても身近な脅威であることを強く示唆しています。
遠い南の島の話ではなく、私たちのすぐ隣で起こりうる問題として捉え、正しい知識を持つことが重要です。
犬がレプトスピラ症に感染する経路

愛犬がどのようにしてレプトスピラ菌に感染するのか、その具体的な経路を知ることは、予防の第一歩です。
主な感染経路
最も一般的な感染経路は、レプトスピラ菌に汚染された環境との接触です。
具体的には、感染した動物(特にネズミなどの野生動物)の尿で汚染された水や土壌に、犬の口や鼻、目の粘膜、あるいは皮膚の小さな傷口が触れることで菌が体内に侵入します。
世界的に見ても、レプトスピラ菌を環境中に広める主な役割を担っているのはネズミです。
ネズミは感染しても症状を示さずに菌を尿中に排出し続けるため、持続的な感染源となります。
稀なケースですが、感染した動物に咬まれたり、その死骸を食べたりすることでも感染する可能性があります。
季節と地域のリスク
レプトスピラ菌は暖かく湿った環境を好むため、日本では特に雨の多い梅雨の時期や、気温が高い夏から秋にかけて感染リスクが高まります。
気温と降水量が多いほど、菌が環境中で生き延びやすくなるためです。
ネズミやアライグマなどの野生動物が多く生息する地域や、水はけの悪い場所は特に注意が必要です。
生活の中での感染リスク例
レプトスピラ症のリスクは、特別な場所だけにあるわけではありません。
私たちの日常生活の中に潜んでいます。
● アウトドアでの活動: レプトスピラ菌は中性または弱アルカリ性の淡水を好むため、川や湖、池などでの水遊び、水泳、キャンプといった汚染された水との接触機会が多い環境は、典型的な高リスクの状況と言えます。海水や乾燥には弱いため、海水や海岸の砂の中では生存できないと考えられています。
● 毎日のお散歩:特に、嵐や激しい雨の後には、汚染された土壌や水が流出し、感染源となる可能性があるため、散歩には注意が必要です。愛犬が散歩中にさまざまなものを口にしないよう、リードは短く持つことをお勧めします。雨上がりの水たまりを飲んだり、その中を歩いたりすることは非常に危険です。また、湿った草むらや水はけの悪い公園、ドッグランなども注意が必要です。
● 都市部や住宅地でのリスク: 近所や公園にネズミが出没する場合、その尿によって土壌が汚染されている可能性があります。リスクを判断する上で重要なのは、「どこに行くか」という場所だけでなく、「どのような環境か」という視点です。「湿っている場所」や「野生動物(特にネズミ)の気配がある場所」は、たとえ都会の真ん中であってもリスクが高いと考えるべきです。神奈川では野生動物のタイワンリスからの感染も危惧されています。
犬のレプトスピラ症の症状

レプトスピラ症の症状は非常に多様で、他の多くの病気と似ているため、飼い主さんが気づきにくいことがあります。 感染しても全く症状を示さないケースから、命に関わる重篤な状態に陥るケースまで、その幅は非常に広いです。
潜伏期間
菌に感染してから症状が現れるまでの潜伏期間は、数日から14日程度ですが、2日から20日程度と幅があります。十分な免疫を持たない個体や免疫力が低下した個体では、重症化しやすいといわれています。
代表的な症状
症状は非特異的で、初期には風邪や胃腸炎と見分けがつきにくいことが多いです。愛犬の小さな変化を見逃さないために、以下のチェックリストを参考にしてください。
●初期症状:
・発熱
・元気や食欲の低下
・体の震え
・筋肉痛による接触嫌悪
・嘔吐や下痢といった消化器系の症状
●重症化した場合の症状:
腎臓障害: 飲水量や尿量の異常な増減、腎機能不全による無尿。
肝臓損傷: 黄疸(歯茎や白目の黄色化)。
その他: 血尿、呼吸困難、鼻血、皮膚の点状出血といった出血傾向などは命に関わる重篤な症状のサインです。
特に急性腎障害と肝不全には注意が必要です。
急性腎障害は、近年犬のレプトスピラ症で最も多く見られる重篤な症状で、腎機能が急速に低下し、尿が作れなくなるなど命にかかわる状態に陥ります。
また、肝臓が障害されると黄疸が現れることがあります。
さらに、血管が損傷すると出血しやすくなり、血尿、鼻血、消化管出血(血便)などが見られることもあります。
早期に治療を開始しないと死亡率が高くなるため、これらの症状に気づいたら速やかに動物病院を受診してください。
無症状キャリア
非常に重要な点として、レプトスピラに感染しても軽症や全く症状を示さない「不顕性感染」、「無症状キャリア」の犬が存在します。
これらの犬は見た目上は健康ですが、尿中に数ヶ月間から一生涯にわたって菌を排出し続け、他の動物や人間にとっての感染源となる可能性があります。
レプトスピラ症は人にも感染する(人獣共通感染症)

レプトスピラ症は、犬だけの病気ではありません。 人間にも感染する可能性があるため「人獣共通感染症(ズーノーシス)」と呼ばれています。 愛犬の健康管理が、ご家族全員の健康を守ることにも繋がります。
人への感染経路
人が感染する経路も、犬と基本的には同じです。
感染した動物(愛犬を含む)の尿や血液、唾液に直接触れたり、それらで汚染された水や土壌に傷のある皮膚や粘膜(目、口、鼻)が接触したりすることで感染します。
愛犬が感染した場合、そのお世話を介して飼い主さんが感染するリスクもゼロではありません。
ただし、人から人へ感染することは極めて稀です。
人が感染した場合の症状
人が感染した場合の症状も、軽症から重症まで様々です。
● 軽症: 多くはインフルエンザに似た症状で、高熱、激しい頭痛、悪寒、筋肉痛、嘔吐・下痢などがみられます。
● 重症 (ワイル病): 感染者の一部は、腎不全、肝障害(黄疸)、髄膜炎、肺からの出血などを伴う重篤な状態に進行することがあります。適切な治療が行われない場合、命を落とすこともある危険な状態です。
家庭での注意点
もし愛犬がレプトスピラ症と診断された、あるいはその疑いがある場合、ご家庭内での感染拡大を防ぐために以下の点に注意してください。
● 手洗い: 愛犬に触れた後や、排泄物の処理をした後は、必ず石鹸と流水で十分に手を洗いましょう。
● 手袋の着用: 尿や嘔吐物などを片付ける際は、使い捨ての手袋を必ず着用してください。
● 消毒: レプトスピラ菌は、熱(50℃で10分間、60℃で10秒間で死滅)、乾燥、酸に弱く、ほとんどの消毒薬で容易に殺菌できます。そのため、尿などで汚れた床や物は、家庭用消毒剤や、塩素系漂白剤の希釈液(水1リットルに対し漂白剤10ml程度)で速やかに消毒することが重要です。また、乾燥に弱いため、しっかりと乾かすことも効果的な対策となります。
● 排尿場所の管理: 愛犬には、人が頻繁に通る場所や、水たまりのできやすい場所を避けて排尿させるようにしましょう。
● 特に注意が必要な方: 小さなお子様、ご高齢の方、妊娠中の方、病気などで免疫力が低下しているご家族がいる場合は、感染した犬のお世話を直接担当することを避けるなど、より一層の注意が必要です。
もし愛犬がレプトスピラ症にかかってしまったら?
野外の水源に触れたり、野生動物との接触後に、愛犬にレプトスピラ症が疑われる症状が見られたら、迷わず、そしてすぐに動物病院を受診してください。
この病気は急速に悪化することがあり、早期の治療開始が予後を大きく左右します。
動物病院では、主に抗生物質の投与と、脱水や腎不全、肝不全といった症状に対する支持療法を組み合わせて治療を行います。
● 抗生物質療法: レプトスピラ菌を殺すために、ドキシサイクリンなどの抗生物質が投与されます。ドキシサイクリンは、血液中の菌だけでなく、腎臓に潜んで尿中への排出を引き起こす「キャリア状態」の菌も排除するのに効果的です。通常、2週間の投薬が必要となります。
● 支持療法:重症化した 多くの場合は入院が必要となり、点滴によって水分や電解質を補給し、ダメージを受けた腎臓を保護します。吐き気止めや栄養補給なども行われます。重度の腎不全に陥った場合には、透析治療が必要になることもあります。
早期に適切な治療を行えば、80~90%の犬が回復するという報告もありますが、残念ながら助からないケースや、回復しても腎臓や肝臓に慢性的なダメージが残り、生涯にわたるケアが必要になることもあります。
愛犬を守る!レプトスピラ症を防ぐ方法

レプトスピラ症は恐ろしい病気ですが、幸いなことに予防する方法があります。 予防は、一つの方法に頼るのではなく、複数の対策を組み合わせることが最も効果的です。
予防接種での対策
レプトスピラ症の予防において、ワクチン接種は最も重要な柱です。
現在日本で一般的に使用されている混合ワクチンには、レプトスピラ症の原因となることが多い複数の血清型(タイプ)の菌に対するワクチンが含まれています。
ただし、ワクチンには知っておくべき重要な注意点があります。
ワクチンの効果は、含まれている血清型に対して特異的であるため、ワクチンに含まれていない型のレプトスピラ菌に感染した場合は、発症を防ぐことができない可能性があります。
つまり、ワクチンは感染リスクを大幅に減らしますが、100%防げるわけではないのです。
だからこそ、ワクチン接種に加えて、後述する日常生活での注意が重要になります。
どのワクチンを接種すべきかについては、お住まいの地域での流行状況や、愛犬のライフスタイル(アウトドア活動の頻度など)によって異なります。
各都道府県の獣医師会は、リスクがどこにでもあるという観点から、すべての犬へのワクチン接種を推奨していますが、最終的な判断は、副作用のリスクなども含めて、かかりつけの獣医師とよく相談して決めることが大切です。
散歩や遊びでの注意点
ワクチンで防御の土台を築きつつ、日常生活で菌との接触機会を減らす努力をしましょう。
●水たまりや、流れの滞った川、池、沼地などの水は飲ませない、入らせないようにしましょう。
●ネズミなどの野生動物が多く生息する場所や、その痕跡(フンなど)がある場所には近づかないようにしましょう。
日常の衛生管理
ご家庭の環境を清潔に保つことも予防に繋がります。
●食器やベッドは定期的に洗浄し、清潔を保ちましょう。
●家の周りからネズミが好むような環境(ゴミの放置など)をなくし、ネズミの侵入を防ぎましょう。
まとめ

レプトスピラ症は、愛犬の命を脅かすだけでなく、飼い主さんやご家族にも感染する可能性のある、決して軽視できない病気です。 しかし、正しい知識を持ち、適切な対策を講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。 この記事の重要なポイントをもう一度確認しましょう。 ●レプトスピラ症は、犬と人の両方に感染する人獣共通感染症です。 ●感染リスクは山や川だけでなく、都市部の公園や水たまりなど、身近な場所に潜んでいます。 ●予防の基本はワクチン接種です。愛犬に合ったワクチンプログラムを獣医師と相談しましょう。 ●ワクチンだけに頼らず、危険な水場を避けるなどの日常生活での注意が、愛犬と家族を守る鍵となります。 愛犬の健康を守るのは、飼い主さんです。 この記事を参考に、ぜひかかりつけの獣医師とご相談の上、愛犬とご家族にとって最適な予防プランを立ててください。












