愛犬に「ちょっとだけ」「人と同じものを」と、愛情表現のつもりで与えた食べ物が、実は深刻な中毒症状を引き起こす危険性をはらんでいることをご存知でしょうか。 私たちの食卓に並ぶ身近な食材の中には、犬の体にとっては有害な物質を含むものが数多く存在します。 この記事では、犬の食中毒や中毒の原因、危険な食べ物の具体的なリストとその科学的な理由、中毒が疑われる際の症状と緊急時の対応、そして何よりも大切な予防法について、網羅的に詳しく解説します。 愛犬の健康と命を守るための正しい知識を身につけましょう。
この記事の監修
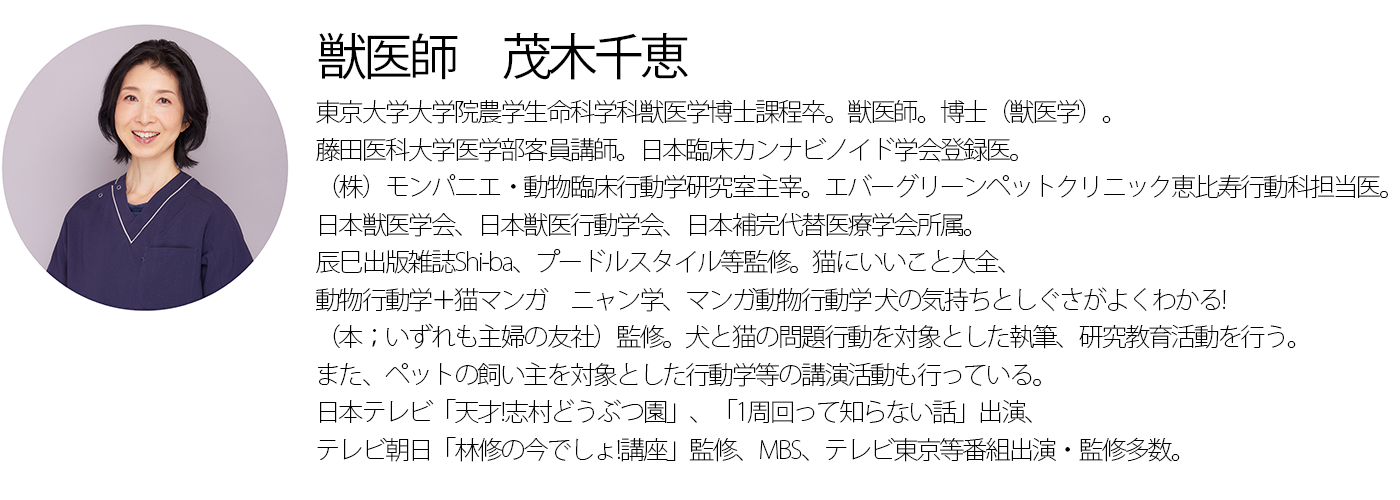
犬が食中毒になる原因とは?

一般的に「食中毒」という言葉は、食べ物が原因で起こる体調不良全般を指して使われがちですが、獣医学的にはその原因によって大きく二つに区別されます。 一つは、細菌やウイルスなどの病原体に汚染された食べ物を摂取することによる「食中毒」です。 もう一つは、食べ物に含まれる成分そのものが犬の体にとって有毒であるために起こる「中毒」です。
食べてはいけないものを口にした場合
この場合は「中毒」に分類されます。犬が中毒を起こす原因の多くは、日常生活の中での偶発的な摂取です。
例えば、散歩中の拾い食い、ゴミ箱漁り、テーブルの上に置かれた人間の食べ物の盗み食い、あるいは飼い主が良かれと思って与えたおすそ分けなどが挙げられます。
チョコレートに含まれるテオブロミンや、ネギ類に含まれる有機硫黄化合物のように、特定の成分が犬の代謝能力では分解・無害化できず、毒として作用します。
また、食品だけでなく、家庭内にある観葉植物(ユリ、サゴヤシなど)や、自然界の毒キノコなども、犬が口にすると重篤な中毒を引き起こす危険があります。
保存状態が悪化した場合
この場合は主に「食中毒」に分類されます。
食べ残したフードや手作り食を室温で長時間放置したり、腐敗した肉や野菜を犬が口にしたりすることで発生します。
特に、日本の梅雨から夏にかけての高温多湿な環境は、食中毒菌の増殖に最適な条件です。
食品がサルモネラ菌、大腸菌、カンピロバクター菌、リステリア菌などの細菌や、カビ(マイコトキシンなどのカビ毒を産生する)などに汚染されると、それを食べた犬は嘔吐や下痢といった消化器症状を発症します。
さらに、 目に見えないカビが作る「カビ毒」も、命に関わるリスクです。
特にアフラトキシンは、トウモロコシなどに発生し、犬に強い毒性を示します。
犬は毎日同じフードを食べるため、毒素が蓄積しやすいです。
2020年には米国で、アフラトキシン汚染フードによる犬の死亡事例も発生しました。
アフラトキシン中毒は肝障害を引き起こし、死に至ることもあります。
カビ毒は熱に強く、目に見えなくても存在するため、フードの適切な管理が重要です。
犬にとって「毒」となる危険な食べ物一覧

犬に絶対NGの食材(中毒症状を引き起こす)
ネギ類(玉ねぎ、長ネギ、にんにく、ニラなど)
- 毒性成分: 有機チオ硫酸化合物(n-プロピルジスルフィドなど)。
- 症状: 摂取後1〜5日と遅れて症状が出ることが特徴です。初期の嘔吐や下痢に続き、貧血の進行に伴い、歯茎が白くなる、元気消失、呼吸が速くなる、赤〜褐色の尿(血色素尿)などの症状が現れます。
- 注意点: 加熱しても毒性は消えません。ハンバーグやスープなど、エキスが溶け出した料理にも注意が必要です。
チョコレート、ココア
- 毒性成分:メチルキサンチン類(主にテオブロミン、カフェイン)。
- 症状:摂取後6〜12時間以内に、嘔吐、下痢、多飲、落ち着きのなさ、興奮、頻脈、不整脈、筋肉の震え、発作などが現れ、重症例では心不全や呼吸困難により死に至ることもあります。
- 注意点: 毒性の強さはカカオの含有量に比例します。ホワイトチョコレートはテオブロミンをほとんど含みませんが、脂肪分が高いため膵炎のリスクがあります。
ぶどう、レーズン、マスカット
- 毒性成分: 正確な原因物質は特定されていませんが、近年の研究では果実に含まれる「酒石酸」が最も有力な原因物質と考えられています。
- 症状: 摂取後数時間以内に嘔吐がみられることが多く、その後、食欲不振、下痢、元気消失が続きます。24〜72時間以内に急性腎不全に進行し、尿がほとんど出ない(乏尿)、あるいは全く出ない(無尿)状態になると、命に関わります。
- 注意点: 毒性を示す量は個体差が非常に大きく、一粒食べただけで重症化した例もあれば、多く食べても無症状の犬もいます。そのためほんのわずかの摂取であっても緊急事態と捉え、直ちに動物病院を受診する必要があります。
キシリトール
- 毒性成分: キシリトール(糖アルコールの一種)。
- 症状: 通常、嘔吐が最初に見られ、嗜眠、運動失調、虚脱、発作などの低血糖の臨床徴候は、摂取後30~60分以内に現れることもあれば、摂取後12時間まで遅れて現れることもあります。
- 注意点: キシリトールは「シュガーレス」「カロリーオフ」と記載のある多くの製品(ガム、飴、歯磨き粉、焼き菓子、一部のピーナッツバターなど)に含まれており、「隠れた危険」と言えます。犬の近くで使用する製品の成分表示を注意深く確認する習慣が不可欠です。
意外と知られていない危険食材
生のイカやエビなどの魚介類
生の一部の魚介類には「チアミナーゼ」という酵素が含まれています。この酵素は、エネルギー代謝や神経機能に不可欠なビタミンB1(チアミン)を分解してしまいます。生の魚介類を長期的に摂取すると、ビタミンB1欠乏症に陥る可能性があります。
- 症状:神経症状が主で、ふらつき、元気消失、眼振、けいれんなどが見られます。
- 注意点: チアミナーゼは加熱によって失活するため、生の魚介を素早く適切に加熱調理すればこのリスクは回避できます。
加工ハム・ベーコン
問題となる成分: 1) 過剰な塩分:高ナトリウム血症を引き起こし、嘔吐や下痢、多飲多尿、重篤な場合は神経症状や腎障害の原因となります。
2) 高脂肪: 急性膵炎の主要なリスク因子です。膵炎は激しい腹痛を伴い、命に関わることもあります。
3) 添加物: 保存料として使用される亜硝酸塩などは、人での研究で発がん性との関連が指摘されています。
生のじゃがいも・芽
- 毒性成分: ソラニン(天然毒素の一種)。ソラニンは、特に緑色に変色した皮や芽、茎や葉に多く含まれます。
- 症状: 嘔吐、下痢、よだれ、腹痛、元気消失などの消化器症状が主です。
- 注意点: じゃがいもは、きちんと皮をむき、緑色に変色した部分と芽を取り除き、十分に加熱調理すれば安全です。
量によって危険になる食べ物
ナッツ類(特にマカダミアナッツ)
- 毒性成分(マカダミアナッツ):未だ特定されていませんが、犬に神経症状を引き起こします。
- 症状(マカダミアナッツ):摂取後12時間以内に、後肢の脱力、歩行困難、嘔吐、震え、高熱などが見られます。致死的ではないことが多いです。
- 注意点: 他のナッツ類も、マカダミアナッツのような特異的な毒性はないものの、脂肪分が非常に高いため、消化器症状や膵炎のリスクがあります。
チーズ・乳製品
- 問題となる成分:問題なのは中毒ではなく「不耐症」です。多くの成犬は、乳糖(ラクトース)を分解する酵素「ラクターゼ」の活性が低いため、牛乳や乳製品をうまく消化できません。
- 症状: 下痢、軟便、お腹の張りや痛みなどの消化器症状が主です。
人間用のパン・ケーキ
- 危険因子: 高い糖分と脂肪分は、肥満や膵炎のリスクを高めます。特に危険なのが、未発酵のパン生地です。犬の温かい胃の中で酵母が発酵し、エタノール(アルコール)と二酸化炭素ガスを産生します。これにより、アルコール中毒と、胃が膨れ上がり捻転する致死的な状態「胃拡張・胃捻転症候群(GDV)」を引き起こす可能性があります。
犬の食中毒の主な症状とは?

中毒の原因物質や病原体によって症状は異なりますが、共通して見られる徴候があります。 早期発見のために、日頃から愛犬の様子をよく観察することが大切です。
初期症状
中毒や食中毒の初期には、以下のような比較的軽度な症状が見られることが多いです。
- 嘔吐
- 下痢
- 食欲不振
- 元気がない、ぐったりしている
- よだれが多い
- 震え
- 落ち着きがなく、そわそわする
これらの症状は他の病気でも見られますが、何かを口にした後に現れた場合は中毒を疑う必要があります。
重症化するサイン
以下の症状は、中毒が重症化し、生命に危険が及んでいる可能性を示す徴候です。
一つでも見られたら、迷わず夜間や救急であっても動物病院を受診してください。
- 血便や吐血(吐いたものに血が混じる)
- けいれん発作
- 黄疸(歯茎や白目が黄色くなる)
- 呼吸が速い、苦しそう、不規則
- 意識がもうろうとしている、呼びかけへの反応が鈍い
- ぐったりして自力で立てない、倒れる
症状が出るまでの時間
- 即時〜数時間で発症: キシリトールによる低血糖は、摂取後30分程度で起こることがあります。チョコレートやマカダミアナッツ、ブドウの初期の消化器症状も、数時間以内に現れることが多いです。
- 数時間〜数日で発症: 微生物による食中毒の場合、菌が増殖するまでに潜伏期間があるため、症状が出るまで数時間から数日かかることがあります。
- 遅れて重篤な症状が現れる場合: 最も注意が必要なのがこのケースです。ネギ類による溶血性貧血は、赤血球が徐々に破壊されるため、目に見える症状が出るまで1〜5日かかることがあります。同様に、ブドウによる急性腎不全も、腎機能が著しく低下するまで24〜72時間かかることが報告されています。
愛犬が危険なものを食べてしまったと判明したら、たとえ症状が出ていなくても、すぐに獣医師に相談することが非常に大切です。
時間差で症状が出ることがあるため、早期の処置が愛犬の命を救う鍵となります。
もし食中毒が疑われるときの対処法と受診の目安

愛犬が危険なものを口にしたかもしれないと気づいた時、飼い主が冷静に行動することが、その後の愛犬の運命を左右します。 冷静になって以下の手順で対応してください。
まずすぐに確認すべきこと
的確な診断と治療を受けるために、正確な情報は不可欠です。以下の情報を確認・確保してください。
- 何を: 食べた物の正確な名前(例:〇〇製菓のダークチョコレート、キシリトールガムなど)
- どれくらい: 食べた量(例:〇〇グラム入りパッケージの半分、ガムを3粒など)。正確な量が不明な場合は、残骸から推測します。
- いつ: 食べたおおよその時間
- パッケージの保管: 食べたもののパッケージや袋、ラベルがあれば、必ず保管して動物病院へ持参してください。成分や含有量が記載されており、治療方針を決める上で非常に重要な手がかりとなります。
やってはいけない自己判断
良かれと思って行った自己流の処置が、かえって状況を悪化させることがあります。以下の行為は絶対に避けてください。
- 獣医師の指示なく無理に吐かせる: 強酸や強アルカリ、石油精製物(ガソリン・灯油系のもの)の場合、吐かせると、食道や口内を傷つける危険があります。また、意識が朦朧としている犬や横臥している犬に吐かせると、吐瀉物が気管に入り誤嚥性肺炎を起こすリスクがあります。
- 食塩水で吐かせる: 昔の民間療法として知られていますが、かえって食塩中毒(高ナトリウム血症)を引き起こし、命に関わる危険があるため、絶対に行わないでください。
- 人間用の薬を与える: 人間用の胃腸薬や鎮痛剤などは、犬にとって有毒な成分を含んでいることが多く、中毒を悪化させる可能性があります。
- インターネットの不確かな情報を鵜呑みにする: 科学的根拠のない民間療法は危険です。必ず獣医師の指示を仰いでください。
動物病院受診の目安
以下の症状が一つでも見られる場合は、緊急性が高いため、直ちに動物病院を受診してください。
- 嘔吐や下痢が短時間に繰り返し起こる
- 便や吐しゃ物に血が混ざっている
- 水やフードを一切口にしない状態が続く
- ぐったりしていて反応が鈍く、自力で立てない
- 呼吸が荒く、落ち着かずそわそわしている
- ふらつきや痙攣のような動きがある
特に、子犬、高齢犬、基礎疾患のある犬は中毒症状が重症化しやすいため、危険物を食べた可能性がある場合は、無症状でもすぐに動物病院に相談しましょう。
夜間や休日に備え、事前に近隣の夜間診療動物病院を選定しておくか、各都道府県の獣医師会が設ける救急動物病院や相談窓口を利用することも選択肢です。
動物病院に連絡する際の伝え方
電話で連絡する際は、以下の情報を簡潔かつ正確に伝えられるよう、事前にメモしておくとスムーズです。
- 犬の情報: 犬種、年齢、体重
- 持病・アレルギーの有無
- 食べたもの: 製品名など、食べたと思われるもの
- 食べた量: おおよその量
- 経過時間:: 食べてからの時間
- 現在の症状
犬の症状からの自己判断が難しい場合は、電話で相談し、指示を仰いでから受診を検討しましょう。
動物病院での治療内容
動物病院では、犬の食中毒治療は、飼い主からの情報と犬の診察に基づいて進められます。
具体的には、まず問診で食べたもの、量、時間などを詳しく確認し、触診や聴診で全身状態を評価します。
その後、必要に応じて詳しい検査や処置が行われます。
【診断のための検査】
○血液検査: 赤血球や白血球の数、貧血の有無、肝臓や腎臓の機能を評価します。
○レントゲン検査・超音波検査: 異物の誤飲が疑われる場合や、胃の拡張などを確認するために行われます。
【体からの毒物除去(除染)】
○催吐処置: 摂取後間もない場合(通常1〜2時間以内、チョコレートなど吸収が遅いものはそれ以上でも有効な場合がある)に、安全で効果的な注射薬を用いて嘔吐を促し、胃の中の毒物を排出させます。
○胃洗浄: 大量の毒物を摂取した場合や、催吐処置が無効な場合に行われます。全身麻酔下でチューブを胃に挿入し、生理食塩水などで胃の中を洗浄します。
○活性炭の投与: 医療用の炭で、消化管内で毒素を吸着し、体内に吸収されるのを防ぎ、便と一緒に排出させます。
【全身状態の悪化を食い止める支持療法】
○点滴治療: 解毒治療において最も重要な治療の一つが、輸液療法です。輸液療法は、脱水状態の改善、血圧の維持、腎臓などの臓器の保護に加え、尿量を増加させることで体内の毒素の排泄を促進します。
○対症療法: けいれんを抑える薬、不整脈を整える薬、肝臓を保護する薬など、症状を緩和するための治療を並行して行います。
中毒症状が重度で、複数の臓器にダメージが及んでいる場合や、継続的な点滴・モニタリングが必要な場合は、入院治療が必要となります。
食中毒を予防するために飼い主ができること

ここまで中毒の一般的な治療法について解説してきましたが、最も重要なのは「予防」です。 日々の心がけで、愛犬を危険から守ることができます。
食べ物管理を徹底する
犬の手の届く場所に危険なものを置かないことが、食中毒予防の基本です。
- キッチンカウンターやダイニングテーブルに人間の食べ物を放置しない。
- ゴミ箱は必ず蓋付きを選び、犬が簡単に開けられないように工夫する。
- 食品庫や引き出しには、チャイルドロックなどを活用するのも有効です。
夏場は特に食べ残しを早めに片付ける
フードボウルに出した食べ残しは、細菌繁殖の温床になります。
ウェットフードや手作り食はもちろん、ドライフードであっても犬の唾液が付着することで雑菌が繁殖しやすくなるため、長時間放置せず、15分経過したら片付けましょう 。
食後の食器は毎回必ずしっかり洗浄して乾燥させておきましょう。
フードの衛生管理と適切な保管
ドライフードは、カビ毒(マイコトキシン)のリスクを避けるため、特に高温多湿を避け、以下の点に注意して保管しましょう。
- 密封して冷暗所に保管: 開封後は空気を抜き、密閉性の高い容器に入れ、直射日光が当たらない風通しの良い涼しい場所で保管します。
- 冷蔵庫での保管は避ける(注意すれば可): 出し入れ時の結露がカビの原因となるため、素早く出し入れすることが重要です。
- 早めに使い切る: 酸化やカビのリスクを避けるため、開封後は1ヶ月を目安に使い切れる量を選びましょう。
家族・子どもにもルールを共有する
家族全員が同じ意識を持つことが、予防の鍵となります。
- 「犬に人間の食べ物をあげない」というルールを家庭内で徹底しましょう。特にお子さんや来客には、なぜ危険なのかを丁寧に説明することが大切です。
- 犬におやつやご褒美をあげたい時のために、安全な犬用のおやつを常備しておき、それを渡してもらうようにしましょう。
拾い食い防止のしつけ
散歩中の拾い食いは、命に関わる事故に直結する非常に危険な行動です。
これは罰でやめさせるのではなく、号令によって犬を安全な行動に導くことが重要です。
- 「ちょうだい」「出して」「オフ」「落とせ」: 口にくわえたものを、飼い主の合図で自発的に離すトレーニングです。おもちゃなどで遊びながら練習し、より魅力的なおやつと交換してあげます。成功したらたくさん褒めて、「離すと良いことがある」と学習させます。
- 「マテ」「そのまま」「ステイ」: 落ちているものに興味を示した時に、それを口にするのを我慢させるコマンドです。犬が落ちているものを無視して飼い主の方を見たら、すかさず褒めてご褒美をあげます。これにより、「飼い主さんに注目する方が良いことがある」と学習させます。
- 口輪の活用: 拾い食いがどうしてもやめられない場合は、散歩中など限定的な状況で、バスケットタイプの口輪(マズル)を使うのも有効な手段です。最近の口輪には、装着したままで水飲み、食べ、舐めができる快適なデザインのものが多く、犬の安全を守るのに役立ちます。
まとめ
犬の食中毒や中毒は身近な食べ物が原因で突然起こり、油断は禁物です。
愛犬の健康を守るには、日頃からの予防管理と正しい知識が不可欠です。
危険な食べ物を置かない、拾い食いをさせないトレーニングを習慣にしましょう。
万が一の際は、迅速に動物病院へ相談してください。












